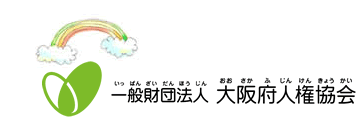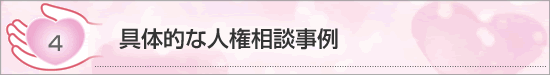(3) 障がい者・児に関する人権相談
地域で発見できた障がい児の人権相談 ~A市人権地域協議会への相談~
<相談のあらすじと対応のポイント>
- 障がいがある子どもの養育意識が低い両親に対し、障がいがある子どもの今後の成長を期待したい支援者たちの活動によって、両親の養育の姿勢が変わったケース。
- 最初は、小学校の教員から、両親の養育意識はあまりにも低く、結果的にネグレクト(児童虐待)になっているのではないかという相談事例。
- 本ケースでは、確かなネグレクトだとは判断し難く、重大な問題に至る可能性もあるので、児童相談所への通報をするまでに地域の支援者が連携し、両親の子育てに関する意識が変わった。
- 一般的に児童虐待は、家庭内という密室で行われるケースが大半で、発見が遅れ被害が大きくなってから支援が開始されることが多い。最悪は子どもが死亡することも珍しくない。虐待をおこなう親はしつけだという意識もあり、支援者が介入する時期を遅らせる。
- 本ケースは、支援者たちが地域社会の中で、孤立していたこの両親と子どもに対し、適切に危機介入(支援)ができたことに意味がある。この家族を支援することによって、地域の社会資源同士の新たな関係が構築され、地域からの孤立を防ぐシステムが構築されたことは大きな意義がある。
相談前・相談後のイメージ 
●相談者からの相談と情報提供の内容
- 小学校の教員より、障がいがあり電動車いすで生活をしている男子生徒(以下、本人)の件で相談が持ち込まれた。
- 父の帰るのが遅くなると、母親だけでは介助ができないので何日も入浴させてもらえないことがある。また、そのことを学校から注意されると保護者は学校へ通わせないことがある。時には両親とも帰宅が遅くなると、単独での排尿ができないため、事前に水分を控えることもあるという。
- 外出は、学校・病院に限られ、その他のところには行けないと本人は思いこんでいる。
- 今後の本人のために、まず外出する楽しさを知って欲しいので、外出のニーズを聞き出してほしいというものであった。
●相談からわかってきたこと
小学校の教員より、担当の障がいのある生徒が両親からのネグレクトによって下記の問題を抱えている、という人権相談があった。今後の生活を考えて、
- 何日も入浴をしていないことがある。
- 学校・病院以外の外出がほとんど無い。
●対応
まず、状況を確認するために、本人と両親に会うための家庭訪問を実施。その結果、次の状況が確認できた。
- 両親は働いており、本人は自分で排泄ができないので、留守番中、水分の摂取を我慢している。
- 本人が住んでいる2階への階段は狭く急であるため、入浴サービスのヘルパーから「安全が保障できない」と改修の申し出があり、ヘルパーのサービスがストップしているが、両親は改修しようとしない。
- 父の帰りが遅くなると、1階へ移動する介助ができないので、何日も入浴させてもらえないことがある、など。
<支援の結果>
- 両親に今の状況は、「ネグレクトに近い状態であること」、「ネグレクトは虐待であること」、を理解してもらうための話し合いを、小学校教員とともに持った。
- 住居は3階建てで、本人の部屋は2階にあるため、浴室も玄関も1階にあり、自分で階下に降りることができないので、入浴も外出も自力ではできない。そのため、住宅改修の補助制度等を両親に情報提供し、住宅改修を実施してもらった。
- 本人に進学も含めた自分自身の将来について考える力をつける意味で、外出等の社会参加の機会を増やす。
- 両親への継続支援の必要性があるため、本人が治療・入所していた障がい児施設のソーシャルワーカーに支援を依頼した。
●支援のために連携した機関等
- 小学校教員
- A市障害福祉課
- 地域コミュニティソーシャルワーカー(CSW)
- 障がい児施設ソーシャルワーカー
Q.「児童虐待」とは
子どもの心身の成長及び人格の形成に大きな影響を与える、子どもに対する重大な人権侵害であり、時には生命までもおびやかす行為。身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待などの行為がある。
Q.「ネグレクト」とは
保護者としての子どもの育ちを著しく怠ること。例えば、子どもの健康・安全への配慮を怠る、食事、衣服、住居等が極端に不適切で健康状態を損なうほど無関心・怠慢、子どもが必要とする情緒的な欲求に応えない、子どもを遺棄する、保護者以外の同居人がする虐待行為を放置することなど。
☆大阪府における児童虐待の実態
- 「児童虐待等の相談状況」【大阪府子ども家庭センター】
(大阪府ホームページ)
☆児童虐待に関する相談窓口
- ●大阪府子ども家庭センター(大阪府ホームページ内)