高齢者の人権相談 ~S市人権協会への相談~
<相談のあらすじと対応のポイント>
単身生活の高齢者(要支援1、83歳、男性)に関する支援の中で、複雑で混乱した状況で、次のような課題整理をおこない、一つひとつ解決に向けて支援したケース。
[課題]
- 本人(男性83歳)と長女の関係が悪いこと。
- 本人の認知症が疑われること。
- 本人と長女の関係が悪化する原因に、財産の問題があること。
- 本人は長女より、介護保険サービス事業所のケアマネージャーとヘルパーを信頼しているが、長女は介護保険事業所に対して不信感を持っている。
- 介護保険サービス事業所は、長女との信頼関係が修復できないと感じている。
相談前・相談後のイメージ 
●相談者の状態と関係者の状況
- 本人(父親)の訴えの内容は、長女が勝手に家に入り、大事なものを持って帰る。長女が財産目当てなので、父親は鍵の交換や区役所で住民票などを勝手に異動できないように手続きをした。また、長女が主張している現状のケアマネージャー(以下、ケアマネ)やヘルパーの変更については、父親としては満足しているため変更する気はない。
- 長女に対して父親の被害感情が強く、最近は長女が家に入ることも拒否している。この件については、被害妄想や認知症の進行も疑われた。
- 長女と介護保険サービス事業所(以下、事業所)との関係も悪化しており、長女は現在のケアマネやヘルパーは全く信頼できないので、ケアマネや事業所を変更したいと主張する。
- 事業所は、長女からの頻繁な電話やサービス中の家族トラブルで、業務に支障をきたしている。長女と話し合いを試みたが、全く関係調整が進まず困っている。事業所は、当事者にとってスムーズなサービスができるように調整したいので、事業所は協力して欲しいと考えている。
このように、三者三様の思いがあり、人権協会が介入した時点でも課題が複雑化していた。
<父親の状況>
- 体の状況:糖尿病、高血圧、軽い脳梗塞
- 障がい:身体障害1級(内部障がい)、視覚障害1級
●人権相談員の対応内容
- 三者(父親・長女・事業所)から状況を聞き、地域包括支援センターのケア会議にて方向性を決定。
- 父親の認知症判断は難しく、かかりつけ診療所によると、「長谷川式」では29点/30点である。
- 父親への支援は、人権協会による訪問とヘルパーや診療所と連携しながら状況を観察する。
- 長女に対しては、父親の拒絶が激しいが、認知症から来ているものかどうか不明であるものの、父親が拒絶する気持ちが強いので、父親とはしばらく距離を置くように助言する。その間は関係者で父親宅を訪問して、体調や日常生活に変化があれば連絡することを説明。
- 一方、事業所へは、長女との信頼関係を再構築するには不可能な状態だと思われることを伝える。長女への父親の日常的状況が変化した場合の連絡は、人権協会を通じておこなう。
- 父親の介護度の区分変更結果までは、現状のケアマネとヘルパーでおこない、介護度の結果により再度ケア会議をもち、当事者と家族が納得する形でサービス及び事業所等を調整する。
- 主治医や事業所と連携し、状況によっては認知症専門機関で受診の可能性あり。
●取り組み内容とケアプラン(支援内容の計画)
Q.「あんしんサポート」とは
認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が不十分な人々などを対象に、地域で自立した生活が送れるように援助し、その権利擁護に資することを目的とするものです。
ご本人との契約に基づいて福祉サービスなどの利用援助や日常的な金銭管理サービス、書類等の預かりサービスといった生活支援をおこなわれます。(社会福祉法人大阪市社会福祉協議会「くらしサポートネット」より引用)
- 地域包括支援センターのケア会議
- 介護保険 区分変更申請
(「あんしんサポート」、「成年後見制度」、「財産管理委任契約」は、説明のみ)
- 家族間の調整は微妙な問題であり、特に金銭面の調整は第三者としては難しい。
(財産など金銭的部分については、時期を見極めて弁護士など専門機関に繋ぐ。) - 父親は83歳と高齢であり、既往症からも認知症が発症していてもおかしくない状態なので、状況により認知症専門機関へ受診を検討する。
- 訪問や関係機関との密な連携により、正確な現状を把握し、父親の希望である在宅生活が快適におこなえるように、長女も含めて家族間の調整をしていく。
●支援のために連携した機関等
- ケアマネージャー
- ヘルパー及び事業所主任
- 区地域包括支援センター
- 介護保険 認定調査員
- 区役所介護保険担当者
- かかりつけ診療所
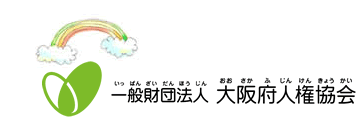
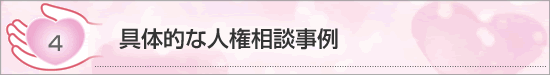
Q.「長谷川式」とは
認知症の評価スケールとして、医療福祉現場などで幅広く使用されているのが改定長谷川式知能評価スケール(HDS-R)です。
この長谷川式スケールは、被験者への口頭による質問により、短期記憶や見当識(時・場所・時間の感覚など)、記名力などを比較的容易に点数化し評価できるようになっています。また、質問者の熟練度にさほど左右されることなく一定の結果が得られ、評価に要する時間も20分前後と一般の心理検査に比べ短いのも特徴です。評価結果については、合計点数30点満点中20点以下が「認知症の疑いがある」と判定されます。