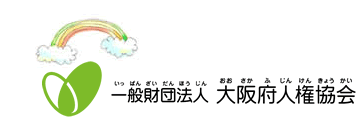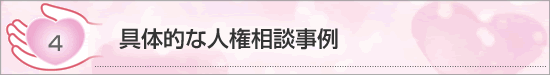(5) 子どもに関する人権相談
~妻から暴言を言われ、子どもに暴力を振るう妻に疲れているお父さんからのご相談~
<相談のあらすじと対応のポイント>
- キーワード:虐待、貧困、精神疾患
- 相談者:夫からの相談
- 家庭状況:夫(相談者、30代前半)、妻(30代前半)、長男(14歳、妻と前夫との子)、長女(3歳)、次女(1歳)
- 相談の主訴:妻から暴言を言われ、子どもに暴力を振るう妻に疲れている。どうしたらいいか。
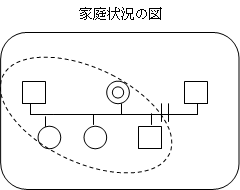
●相談の経過
父親が人権文化センターの相談所へ来所し、面接相談を行った。
●相談内容および生活歴
- 子どもへ暴力をおこなう妻のことで悩む夫からの相談。家庭は、妻と前夫との間に生まれた中学生の息子1人と夫婦の間に生まれた3歳と1歳の女児2人とすごす5人家族で住んでいる。
- 妻は、初婚のときに生まれた中学生の子どもに対して、子どもの返事の仕方が悪い等の理由でミミズ腫れができるほど叩くことがあり、中学生の子どもは児童養護施設に過去2回入所した経験がある。
- 妻は、普段はこまめに育児や家事をおこなうが、精神疾患があり些細なことでキレやすく、夫に対しては「役立たず。全てあなたが悪い。」などと一方的に責めることが多いとのこと。些細なことから夫婦喧嘩となり、あまりの妻からの暴言に夫は傷つき、過呼吸となって意識が危うくなった。そのため、病院に緊急搬送されて入院となり、医師からうつ病と診断されている。
- 夫は、子どものことが心配になったので、医師の了解のもと、入院して2日後に薬を渡されて退院し、すぐに相談窓口に来所。
- 夫は、妻のいる家には帰りたくないが子どもが心配でどうしたらいいかわからないと悩んでいる状況である。
●対応
- 児童虐待を発見した場合、すぐに発生した場所の市町村児童家庭相談窓口か児童相談所(子ども家庭支援センター)へ通報することが必要となるため、本事例においても虐待の状況について事実確認が重要となる。
- 夫に妻が子どもに対して行っている行為は児童虐待であることを伝えることや児童虐待についての説明、お住まいの市町村の児童家庭相談窓口と児童相談所(子ども家庭支援センター)を紹介する必要がある。
- しかし、夫は通報をためらうことも考えられ、原因は自分にある、自分が悪いと感じてしまうことも考えられる。その場合、夫の気持ちやこれまでのご家庭内でのしんどさ、お父さんが耐えてきたことなどを受け止めることが必要である。そのうえで、一人で考えこんでしまう可能性があるため、一緒に考えて行きましょうと伝えることも大切である。
- 中学生の子どものみに児童虐待が確認できているが、夫妻の間に生まれた子どもへの虐待の可能性も視野に入れながら支援に取り組むとともに、中学生の子どもが児童養護施設に入所した際の状況やそのときのお話をお父さんから聴いておく必要もある。
- 医師からうつ病と診断されているため、精神的ケアについて専門家(医師や精神保健福祉士)や保健所とのつながりや支援方策を検討する必要がある。また、医師等の相談のもと、お父さんの父母やきょうだい、友人などの周りにいる人でお父さんを支えることのできる人材を見つけ、協力を得られるよう準備を進めることも必要となる。
●評価および今後課題
- 児童虐待としての対応としてどうすべきか考えなければいけない事例である。夫に対して児童虐待の状況の確認を詳細に行い、通報についても検討が必要になってくる。
- 虐待についてはきょうだいに対しても虐待の事実の確認が重要であるため、保健師などによる家庭訪問から子どもの健康状態の把握が重要である。
- 身近な相談窓口として、子育て支援センターや子ども家庭支援センターなどの相談窓口の活用や地域の民生委員などの人材の活用。母親への子育てへのストレスに対して、サークル活動の紹介や虐待状況に対するソーシャルスキルトレーニングの場の紹介なども考えられる。
●連携が想定される資源
- 医療機関
- 保健所(センター)
- 子ども家庭支援センター
- 児童相談所
- 子育て支援センター
- 子育てサークルまたは子育て支援グループ
- 児童養護施設
- 民生児童委員
●利用が想定されるサービス
- こんにちは赤ちゃん事業
- 虐待防止のためのソーシャルスキルトレーニング
- 親学習プログラム