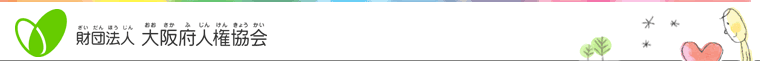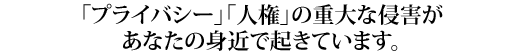|
 |
 |

| 産経新聞大阪府内版掲載【2006年3月30日(木)朝刊】 |
 |
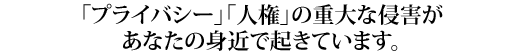 |
 |
|
(プロフィール)
見城 美枝子(けんじょう みえこ)さん
青森大学教授 エッセイスト ジャーナリスト
3男1女の母、群馬県出身。早稲田大学大学院理工学部研究科修士修了。同博士課程に進み日本建築の研究をはじめる。 TBSアナウンサーを経てフリーに。海外取材を含め55カ国以上を訪問。現在、青森大学社会学部教授。建築社会学、メディア文化論、環境保護論を講義中。また著作・対談・講演・テレビなどでも幅広く活躍している。 |
 |
|
「差別」は人間の根源にかかわる問題 時代と共に考えていく必要がある。
「差別」というのは、人間の根源にかかわる問題だと思うのです。子育てを通しての実感ですが、乳児は母親のおっぱい以外のものが口に入ると、本能的に吐き出します。「異質なもの」を否定することで自と他を区別し、自分を守るのです。この区別は自己を確立するためにも必要なのです。人は自分と違うものに対してはまず「否定」から入ります。さまざまな差別意識の根底には、そんな人間の習性があると思います。そこを抜きにして単に「差別はいけない、いい人になりましょう」というだけでは、問題はなかなか解決しないでしょう。
また、人権問題は時代と共に考えていく必要があると思っています。たとえば情報技術の進歩につれ人権問題のあり方も変わります。インターネット上の人権侵害が問題になっていますが、ネット上に流出した個人情報は宇宙に流れ出たのと同じで回収不能だと聞きます。テクノロジーだけが先行し、それに伴う人権問題への対処の仕方が確立されていないのです。時代の中で問題をつねに捉え直し、ルールを改革していくことが必要です。
「想像力」を伸ばすのは教育の役割 まず、差別や偏見の実際を学ぶこと。
大切なのは、まず違いを認め合うこと。その上で、相手の立場に立って考え、相手の痛みを感じることです。これは口で言うのは簡単ですが、実際はとても難しいことです。相手の立場に立って考えたり感じたりするには、豊かな想像力が必要とされますから。けれどもそういう想像力を身につけることが、本当の意味での「教養」なのだと思います。
子どもたちに豊かな想像力を身につけさせるのは教育の役割です。「自分と違うもの」を否定しようとしたときに、「大丈夫、受け入れていいんだよ」と教えてあげることが大事です。そうやって“好き嫌い”がすこしずつ無くなっていく中で、お互いの違いを個性として尊重し合えるようになり、相手の立場に立てる人間になっていきます。まず歴史や社会について見聞を広め、どんな違いが、いかにして生まれてきたかを知る。そして、いま、どのような差別や偏見があるのかを正しく認識する。そこからすべてが始まるのだと思います。 |
 |
 |
 |
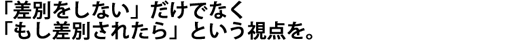 |
(プロフィール)
北口 末広(きたぐち すえひろ)さん
近畿大学 教授
1956年4月大阪市生まれ。京都大学大学院(法学研究科修士課程)修了。国際法・国際人権法を専攻、近畿大学教授として人権法・人権論を教えるほか、ニューメディア人権機構理事兼事務局長を務める。著書に『人権ブックレット55 人権社会のシステムを 身元調査の実態から』(解放出版社、1999年)、『変革の時代・人権システム創造のために』(解放出版社、2005年)など多数。
|
 |
いけない、とわかっていても 利害が関わると“差別する側”に。
30年前の「部落地名総鑑」事件を原点に就職において「社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない」ことが1999年に法律で定められました。しかし結婚の際など、残念ながらこうした差別調査は現在でも行われています。本人に無断で取得された戸籍謄本が、地名総鑑と照合されていた疑いが強まっています。
差別問題は倫理的に捉えるだけでなく、科学的に解明していく必要があります。差別はいけない、と認めている多くの人々が、自分の利害に関わると“差別する側”にまわってしまうという現実があります。この30年間で差別問題に対する社会全体の意識はかなり高まりましたが、いくら数が減っても“差別される側”の個々人が受けた深い痛みは変わらないのです。
人権問題はますます高度化・複雑化 「今何が起こっているのか」を知る。
逆に、利害に関わって、差別しない側になると自分にプラスになる社会システムが必要です。社会構造の変化やテクノロジーの高度化を背景に、人権問題もどんどん高度化・複雑化しています。それに対応していくには最も進んだ人権水準と柔軟な認識が必要になります。当然ですが「知られない人権」は守られません。まずはどんな人権侵害があるのか「現実」を知り、問題意識を持つことが大切です。 時代と共に法律も徐々に整備され、人権を守る社会のシステムが作られつつあります。しかしそこで最も基本になるのは、私たちの意識。一人ひとりが差別の「加害者にならない」だけでなく「自分がもし被害を受けたら」という視点で考えることが重要なのです。
【部落地名総鑑事件】
1975年、全国の被差別部落の地名を載せた図書「部落地名総鑑」が販売され、企業などが購入していた問題が発覚。これに関して法務省が調査を実施し8種類の地名総鑑を確認するとともに発行者や購入者に勧告。1989年には法務省から同事件の終結宣言が出されていたが、2005年・2006年、大阪市内において第9、第10の地名総鑑が発見された。
【戸籍謄本不正取得事件】
2004年、大阪府や兵庫県の行政書士らが戸籍謄本などを不正に取得し、調査業者に販売していたことが発覚。弁護士、行政書士など8つの資格職は「職務上請求書」によって個人の戸籍謄本等を取得できるが、これらの行政書士は調査業者の依頼を受け、「職務上請求書」を悪用して大量の戸籍謄本を取得・販売していたもの。調査業者は取得した戸籍と部落地名総鑑を照合することで差別身元調査を行っていたと見られる。 |
|
|