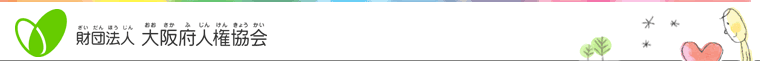
|
|
|
| 新着情報 | |
| 人権トピックス | |
| 講座・イベント案内 | |
| 刊行物・書籍 | |
| メールマガジン発行 | |
| 愛ネットニュース | |
| 人権情報誌 そうぞう | |
| 大阪府人権協会ニュース | |
| 大阪まちづくり プラットホーム |
|
| リンク集 | |
| 組織・事業の概要 | |
| 大阪人権センター | |
| 個人情報保護方針 | |
| お問い合わせ | |
| (C)財団法人 大阪府人権協会 | |
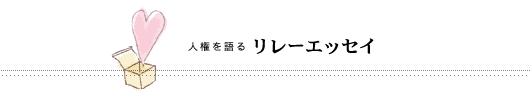 |
 |
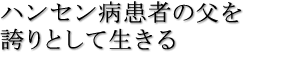 九州大学非常勤講師 林 力(はやし・ちから)さん |
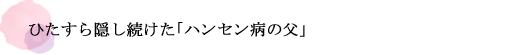 |
私の父は、ハンセン病患者でした。そのことを30年前に明らかにするまで、ひたすらに父の存在を隠して生きていました。 なぜ、父のことを明らかにする気になったのか。それは教師という仕事を通じて、差別と向き合う子どもたちや部落解放運動に打ち込む人々と出会い、多くのことを学んだからです。しかし元々は部落に対する差別意識をもつ人間でした。 |
 |
発病前の父が長崎での商売に失敗し、追われるように一家で博多へ出てきました。炊事場やトイレは共同、隣家の音や匂いまでも共有するような長屋に住み着いたのですが、200メートルほど先にはさらにすさまじい有様の被差別部落がありました。周囲のおとなたちは「部落は怖い、穢れている」と言う。その言葉と悲惨な生活の様子が重なり、幼い私のなかに差別意識が根付いていったのです。 戦後、小学校の代用教員に採用されました。子ども好きでしたから朝から晩まで子どもらと一緒に過ごし、校区の人たちからは「よか先生」と言われるようになりました。けれども部落に対する差別意識はもち続けていました。学校で時々、窓ガラスが割られたり花壇が荒らされたりといった事件が起こります。すると必ず「どこの子かいな」「そげなことするとは"あそこ"たい」「そやな、"あそこ"たい」という会話が教師の間で交わされます。私も当たり前のようにその会話のなかにいました。 |
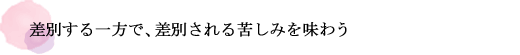 |
"あそこ"とは部落のことです。今思えば、子どもたちは花や金魚を打ち捨てることで、「わしらのことを何もわかろうとせず、花や金魚でごまかすな!」と心の叫びを発していたのでしょう。でも当時は何もわかっていませんでした。 しかし一方で、私自身もハンセン病患者の息子として差別を受けていました。「腐れの子」と言われ、小学校時代の6年間、誰ひとりわが家へ遊びに来ませんでした。ハンセン病患者の家族であることを隠すため、東京へ逃げたり、一家揃って遠縁のおばあさんと養子縁組をして苗字まで変えました。初めて恋愛をした女性は同僚教師でした。しかし刑事の調査を通じて私の父がハンセン病患者だと知った翌日から、二度と目を合わせようとしませんでした。そして数ヵ月後、教育委員会直々の人事によって遠方に異動していったのです。 部落に対する差別意識をもちながら、ハンセン病患者の息子として差別を受けていた私は、どこかでひっかかりを感じていたのかもしれません。1956年、日教組の教育研究集会に参加した私は初めて「同和教育」という言葉を知り、仰天しました。地元に帰るとすぐに「福岡市同和教育研究会」をつくりました。これが九州における同和教育の始まりです。 |
 |
それでもまだ「部落が怖い」という気持ちはありました。しかし、友人の紹介で部落解放同盟福岡県連を訪ねた時のことです。「これから同和教育をやろうという先生ばい」と紹介された私に、ひとりの男性が涙をボロボロこぼしながら「学校の先生が俺たちと一緒にがんばるって? 俺はそげな時代がくるとは思わんやったねえ」と言われたのです。この涙と言葉に、私のほうが勇気と安心感をもらいました。 とはいえ、これまで差別的な義務教育を担ってきた私たち教師が、部落の人々から簡単に受け入れられたわけではありません。「教師、帰れ!」と言われながらも通い続けるうちに、自分たちを拒否する部落の人々の背景が少しずつ理解できるようになりました。すると部落の子どもに対する見方が変わる。自分たちの差別性を自覚すれば、授業や生活指導が変わる。こうなってくると部落へ行くのが楽しくてたまらなくなりました。 |
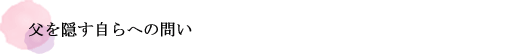 |
1963年の狭山事件をきっかけに、部落の子どもたちに部落民としての自覚をもたせることが強調される時代がきました。多くの子どもたちが「部落民宣言」をしました。部落民宣言は一度やれば取り返しがつきません。一部の教師がイデオロギー先行で強引に宣言させている様子も見られ、私は危ういものを感じていました。その一方で、かなりの子どもたちが自分の社会的立場を明らかにしていくことに取り組む姿が、私自身にはね返ってきました。「おまえはなぜ父を隠す?」と。 さまざまな逡巡を経て、ようやく私は「父は立派な人間だった。ハンセン病であったことは何ら恥じることではない。恥でないことを恥とする時、本当の恥となるのではないか」と思い至ったのです。それを教えてくれたのが、部落解放運動であり、部落の子どもたちでした。私の人生は、部落問題とハンセン病が縄のようにからみ合っているのです。これは本当に素晴らしいことであったと思います。父のことを書き残したいと思い、いろいろと調べました。調べれば調べるほど、父の苦悩、父の偉大さを知り、心が躍ります。今は心から父を誇りに思っています。 |
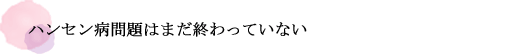 |
残念なことに、私のようにハンセン病患者の家族であることを明らかにできる人は、今もほとんどいません。1996年に「らい予防法」が廃止され、2004年には国賠訴訟で、元患者側の全面勝利判決が下されました。ハンセン病回復者が名実ともに社会復帰できる状況がようやくととのったわけです。 しかし決して問題が本質的に解決したわけではないのです。「家族が名乗り出ないので社会復帰の準備が進められない」という話をよく耳にします。家族が何のためらいもなく、「うちの親はハンセン病にかかって、あそこの療養所で暮らしていたんだよ」と言える社会になった時、ハンセン病問題はひとつの峠を越えたと言えるのではないでしょうか。 |