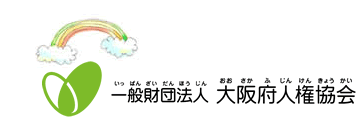2025年度人権NPO協働助成事業
「事業説明・中間報告交流会」を開催しました。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人権NPO協働助成事業「事業説明・中間報告交流会」を8月23日、HRCビルで開催しました。
半年コースの事業説明会と1年コースの中間報告会を同時開催とし、半年コースと1年コースの団体交流、団体相互の協働のきっかけづくりとしました。
1年コース助成団体からは、事業成果(効果)の中間報告、半年コース助成団体からは、事業内容の発表をいただいた後、推進委員からコメントをいただき、後半は団体同士で情報交換をしながら交流しました。
最後に、推進委員の田村太郎さん(一般財団法人ダイバーシティ研究所)と柳瀬真佐子さん(市民ネットすいた)から、報告を受けての意見や、今後に向けてのアドバイス等をいただきました。支援される人支援する人とわけるのではなく、ともに助け合う・学び合うという、そうした工夫をいれてみてはどうか、というお話がありました。例えば、若い世帯は在宅で避難することが多くなり、避難所に来られる人は高齢者と外国人が多くなることが想定されます。それぞれに得意なことを活かしあう、という対策を事業後半にむけて取り入れていってほしい、などのご意見をいただきました。
交流では、団体の強みや提供できること・連携してほしいことを出し合い、団体同士が協働できるきっかけづくりを行いました。
発表された「防災学習」をうちでもやってほしい、といった要望がさっそく出てきました。また、連携してほしいことについても、当団体でつながりのある団体をご紹介するなど、協働や働きかけを図りながら事業を進めていっています。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
<1年コースの中間報告概要>
〇特定非営利活動法人 スイスイ・すていしょん
今までの活動:子ども食堂開催中に災害が起こったらどうするか、災害への備えを意識づける。特にひとり親家庭では災害が起こった時に孤立しやすいのが課題。
郊外学習として、JA東びわこ農協との田植え交流会を実施。行きかえりのバスの中において、災害学習レクレーションとして、基本的な防災の知識を学ぶとともに、加島地区の防災マップなどを見ながら日頃の備えについて学ぶ機会とした。その際、参加者を対象に行ったアンケートの結果から、約2/3の家庭が災害時に家族としてどのように行動するかについて、あまり話し合っていないことなどがわかった。
課題:団体内で、対象をひとり親家庭に限ると、当事者が参加しにくい、共働きなどで家に保護者がいない家庭もある、などの意見があった。
今後:前半の取り組みを踏襲しつつも微調整しながら、アウトカムの達成に向けて事業を展開するために、ひとり親家庭や共働き家庭の子どもたちが、防災の意識を高め、災害発生時に自ら行動し災害に対応できるよう学習を進める。アベノタスカルの見学や楽しく学べる防災教室を実施予定。一緒に体験したり学んだりすることを通して、子ども同士のつながりを深める。
〇識字・日本語研究会
今までの活動:大阪府下に200ほどある識字・日本語教室において、「しきじでぼうさい」プログラムを実施する教室を募集。教室により温度差がかなりあるが、プログラムが5つからなりたっており、すべてのプログラムを実施するのか困難であるように見受けられた。
課題:普段から教室参加者同士が学び合える環境である教室はプログラムに参加しやすいが、そうでない教室はプログラムに参加しづらい。しかし、そうした教室にこそ取り組んでほしいというジレンマがある。そのため、そうした教室には講師を派遣するなどを検討している。
今後:あべのタスカルに訪問予定だったが、すでにいったことがある教室が多数だったため、行先を「人と防災未来センター」に変更。大阪府内の識字・日本語教室、夜間中学関係者らが集まる「よみかきこうりゅうかい」分科会や識字・日本語学習研究集会で報告予定。
〇特定非営利活動法人 KARALIN
今までの活動:事前会議としてオンライン会議7回、対面会議4回、準備作業3回。
子ども防災教室:2回実施(8月)。ユーススタッフとして、高校生スタッフ1名が参加し、子どもとの接点やつなぎ役として機能した。また、地域協力団体として防災士、防災リーダー、校区まちづくり協会、放課後児童室等と協働しながら防災教室を実施することができた。
課題:低学年にとっては内容がやや難しい場面もあり、クイズの難易度や説明の工夫が必要と感じた。指導者によって進行の雰囲気が大きく変わるため、全体的にやわらかく、子どもが安心して発言できる場づくりが求められる。子どもが「今日何をするか知らずに来る」ケースもあり、事前広報の改善(ポスター掲示など)の必要性を感じた。
今後:子ども防災教室の事前アンケートと事後アンケートの変化や内容の分析を行い、子どもの意見を集約し、地区防災計画への反映を行う。子どもの声をどう計画に反映するかについて、校区まちづくり協議会・防災士らとの連携を深めながら具体化する。
12月には親子防災×ECOキャンプを実施予定。防災士と協働した体験型プログラムを開発。計画と準備を進め、実施に繋げる。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
<半年コースの事業計画予定概要と推進委員からのコメント>
〇一般社団法人 両国人権福祉交流センター
予定事業:独居高齢者が多い市営住宅近くでの「みんな食堂」を実施している。そこに防災のアンケートやヒアリングを行い、両国ならではの課題の洗い出しをする。
推進委員より:高齢者の情報を多くもっているところ、例えば病院など、地域資源と連携することなども有用。また地域のキーパーソンとなっている人とうまくつながることができればよりよいのではないか。
〇特定非営利活動法人 こどもの里
予定事業:50年近く西成区萩之茶屋で子どもの居場所づくりをしている。2年前に新たに南津守にも子どもの居場所をスタートした。火曜~土曜主に小学生の居場所となっている。まち歩きをしながら危ないところを発見したり、どこに避難するのがいいのかなど、月一回子ども会議を実施しているので、そこで話合えたらと考えている。また防災をきっかけとして、保護者等ともつながりを持ちたいと考えている。
推進委員より:防災は、誰しもが共通して課題として捉えられることなので、それをきっかけに保護者の様子ということを聞き出していくっていうのはすごくいいな思う。子どもは1/3は睡眠、1/3は学校(行けない子もいるが)、1/3は家庭で過ごしている。保護者等の関わりは重要なので、地域でサポートして、一緒に子どもたちを育てていけるように、難しいが取り組んでほしい。