
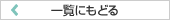
...令和2(2020)年度 第4回...
新型コロナ感染拡大とともに広まる人権侵害
起きていることを知り、差別に加担しない行動を

公益財団法人反差別・人権研究所みえ
常務理事兼事務局長
松村元樹さん
(写真:Masaru Goto/Reminders)
 感染者に対する差別の広まりと激化
感染者に対する差別の広まりと激化
2020年初頭から新型コロナウイルスの感染が広がり始めると同時に差別や人権侵害があちこちで見られるようになりました。私が所属する反差別・人権研究所みえ(ヒューリアみえ)がおこなっているネットのモニタリングでも2020年1月中旬から差別的な投稿を把握しています。また、具体的には県内で感染者が出た地域を名指したうえで「死んでいい」「出て行け」といった内容の書き込みが非常に多く見られました。同時に実際に感染した人や家族に対する人権侵害も起きています。
私が相談を受けた事例をご紹介します(ご家族の承諾済み)。ある大学生は県外の大学に進学し、ひとり暮らしをしていました。新型コロナウイルスの感染拡大のため休校となったので実家に戻ったところ、3日後に発熱。PCR検査で陽性が判明しました。
そのことが三重県のホームページで公表される前に「あの家の子どもが感染したらしい」と広まってしまったのです。その結果、次々と人権侵害が起こりました。
家族がガソリンスタンドで給油して帰宅した直後、スタンドの店長から「しばらくうちに来ないでほしい」と「利用拒否」の電話がありました。本人が行ったこともないパチンコ店や飲食店で「見た」という噂が流されたり、「おまえの子どもは感染者らしいな」「出て行かせろ」と脅すような声色のメッセージが留守電に入っていたこともあります。
ご家族はとても心を痛め、「子どもの名誉を回復したい」と模索されましたが、最終的には何もアクションを起こさないことを選択されました。反論することによってさらなる反感を呼び、感染した子どものきょうだいを含めてさらに人権侵害を受けるかもしれない。もしかすると地域で暮らしていけなくなるかもしれないという恐れと不安があったからです。「ネットと現実は違う」という意見もありますが、ネットの情報から個人を特定され、デマや憶測を信じ込んだ人たちによる嫌がらせや差別を受ける事例が現実に起きています。
 過去に学ばない結果が今につながる
過去に学ばない結果が今につながる
私たちはこれまで部落差別を中心に反差別、人権尊重の取り組みを進めてきました。今回新型コロナウイルスに感染した人たちに対する差別、人権侵害を見ていると、他の差別との「重なり」を感じる部分があります。
ひとつは厳しい差別を受けて声をあげた時、それが事実上「自分はマイノリティーである」というカミングアウトになることです。そのことでさらにひどい差別を受けるのではないかと恐れ、被害を受けても黙って耐えることを選ばざるを得ない。被差別部落出身者や在日外国人、障がいのある人たちも長くそうした状況にありますが、新型コロナの感染者に対する差別にも同じことが起きています。また、感染者が出た地域が強調され、その土地に住む人たちもひとくくりに忌避の対象になるというのも部落問題に似ていると感じます。感染症でいうと、かつてハンセン病に対するすさまじい差別がありました。感染した人はもちろん、家族にも厳しい差別と排除がなされ、一家離散、家族の話もできないという過酷な状況へ追い込まれた人がたくさんいます。こうした歴史から私たちは何を学んできたのかと思うと、非常に残念です。
 自分がデマの発信源にならないために
自分がデマの発信源にならないために
政治家やコメンテーターが差別を誘発する発言を繰り返していることにも危機感をもっています。政治家や有名人の発言ひとつで、ネットでも現実でもひどいバッシングが始まります。「夜のまち」という表現で飲食業や接客業で働く人に対するバッシングが強まったのが一例です。これまで生活保護を受給する人に対して揶揄(やゆ)や批判をする発言が繰り返されたため、「がんばってきた自分たちがコロナで苦しい思いをしているのに、税金で暮らしてきた人間に給付金まで出すのか」というバッシングも起きました。メディアで発言するような立場の人はその影響力に自覚的であってほしいと思います。
差別をなくすために、私たちにできることがあります。まずはメディアリテラシーです。メディアやネットの発信を鵜呑(うの)みにせず、根拠や情報源をできるだけ確かめることです。
自分がデマを発信する側になる可能性もあります。最初は「飲食店に行ったんじゃない?」という憶測が、次の人に伝わる時には「飲食店に行った」となり、やがては「あの店で見た」という話になっている、ということはよくあります。知っている人からの話だからこそ無批判に信用し、他の人に話してしまいがちですが、問題はそれが差別や人権侵害につながること。もっともらしい話を聞いた時は、憶測か事実かをよく確かめ、人に話すことには慎重でありたいと思います。そしてやはり歴史と過ちから学び、教育現場で伝えていくことと併せてメディアリテラシーの学習に取組むことが大切です。
 人権を守る社会が感染拡大を食い止める
人権を守る社会が感染拡大を食い止める
新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから、多くのメディア取材を受けてきましたが、事例としてご紹介できるのは3例ほど。さらなる人権侵害を恐れ、匿名であっても「話さないでほしい」と言われます。また、私の実感と実際の相談件数には開きがありますが、相談がないのではなく、「できない」のが実状ではないかと感じています。追い詰められた人たちの精神状態と生活が心配です。
感染した人や家族を責め、排除するのは、不寛容な社会をつくっていることに気づいてほしいと思います。また、差別を恐れ、感染を公表できない社会は感染の広がりを抑えることも困難でしょう。誰が感染しても「元気になって戻ってきて」と言えるようなコミュニティーや職場、社会をつくる。それがもっとも有効な感染対策だと考えます。
具体的な取組のためには、人権侵害の状況を可視化していくことも必要です。ヒューリアみえでは、2020年6月と9月に三重県内の市町に新型コロナウイルスの差別や人権侵害に関する取組状況と相談事例の照会を行いましたが、既存の相談窓口からは相談事例がほとんどあがってきませんでした。差別や人権侵害の被害者が救済されていくためにも、事例や取組を積み重ね、何かあったら黙るのではなく相談できる取組づくりが求められていると思います。
(2021年1月掲載)


