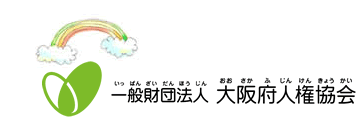外国人市民との共生のために、多方面との協働
公益財団法人とよなか国際交流協会
1.取組~事業内容
(1)活動の基本理念
平成11(1999)年に出された次の基本理念に基づき、主に女性と子どもの場づくり・人づくりをめざした活動が行
われています。
「市民の主体的で広範な参加により、人権尊重を基調とした国際交流活動を地域からすすめ、世界とつながる多文化共生社会をつくる」
(2)事業の柱建てと内容

次のような柱建てと内容で29の事業が行われています。
①多様な人びとが尊重される地域づくり
・市民主体の国際交流活動推進事業(情報サービス、市民協働推進のための「共同デスク」、留学生・ホストファミリー)
・おとな国際事業(とよなかにほんご、にちようがちゃがちゃだん、おやこでにほんご、もっともっとつかえるにほんご)
・持続可能な地域づくり事業(メディア・リテラシー市民ゼミナール、ESD連絡会議)
・ひとづくり事業(ボランティア研修(※写真右上)、哲学カフェ、市民セミナー)
・子ども国際事業(韓国・朝鮮のことばとあそびのつどい、おまつり地球一周クラブ)
②周縁化される外国人のための総合的なしくみづくり
・おとなサポート事業(相談サービス、地域連携ネットワーク)
・子どもサポート事業(多文化子ども読書推進、多文化子ども保育「にこにこ」、多文化子育て支援ボランティア養成、学習支援サンプレイス、子ども母語)
・多文化子どもエンパワメント事業(こども日本語、若者支援)
③学校とつながってつくる豊かな未来
・学校連携事業(小学校外国語体験活動事業、豊中市国際教育推進協議会、渡日児童生徒学校生活サポート事業)
(3)関わる人たち
国際交流センターの年間利用者8万人(外国人4割)
スタッフ14人、事業ボランティア約500人
(4)活動で大事にしていること
この25年の活動の中で見えてきたのは、不法就労・DV・貧困など外国人の中でもより支援が必要な立場に置かれている女性や子どもの問題です。
そういった、社会の中で「周縁化」されやすい女性と子どもを中心にすえ、権利保障とエンパワメントを行い、そのために提言を行政に行っていくことを大事にしています。
また、そういった課題を解決していくためにも、市民協働や連携の強化に力を入れています。
(5)予算
主な収入は、受託費と助成金で、他に会費・寄付・事業の売上などがあります。
2.きっかけ~事の起こりや着火点
(1)設立の経緯
とよなか国際交流協会は、1989年に市長の依頼により発足した豊中市国際交流委員が出した1991年の提言、「豊中市の目指す国際交流」を受ける形で、豊中市が交流協会と国際交流センターを設立したという歴史を持つ団体です。
現在、交流センターの運営は、プロポーザル方式による指定管理制度が導入され、国際交流協会が指定管理団体となっています。
(2)予算の見直しが活動理念や哲学を再確認する機会に
団体設立当初より、豊中市からの補助金により事業を行っていましたが、市の出資財団の「あり方」検討などを受け、予算の削減や運営の指定管理者制度の導入など、事業内容や団体の方向性について変更せざるを得ない状況になりました。
この機会に、何のために団体は存在し、何を目的にしていくのかが団体内で徹底的に話し合われました。
結果、「周縁化された外国人の権利保障とエンパワメントと、そのために行政などに提言を行っていく(アドボカシー機能を持つ)」ことが確認されました。
3.取組が実った要素~実現に導いたモノ
(1)事業を貫く視点とそこに立ち返る評価軸がある。
事業実施においては、次の3つの視点をもった取組が行われています(3つの視点は、事業評価の評価項目でもある)。そのことにより、スタッフだけでなくボランティアの方など、取組に関わる全ての人がはっきりとした目的意識を持つことにつながっています。
①居場所の視点~外国人が安心して居ることのできる場所をつくる。
消費されない・排除されない居場所。
②エンパワメントの視点~奪われた力を取り戻すことができる
それを生み出すためすべての人の参加を保障する。
③ボトムアップの組織づくりの視点~民主的なプロセスでつくられる組織
参加するみんなが活かされる。
(2)ボランティアも事業運営の主体となる仕組みづくり
①事業評価会

国際交流協会では、年度末にその年度に実施した事業の評価会(写真 右記)を行っています。評価会には各事業のボランティアが参加し、実施事業の検証と次年度に活かす点を考えていきます。
②スタッフはコーディネート役に徹する
スタッフは、ボランティアの自主性や自発性を大事にしながら活動を進めていきます。
③ボランティアが現場からあげてくるアイデアを柔軟に事業化。
ボランティアが現場で感じた意見も取り入れながら事業がつくられていきます。
一例として...。外国人ママは子どもが中高生になると行政の子育て支援やPTAのつながりなどがぐんと減るけど、そんな時期だからこそ相談したい、地域とつながっていたいと思う時があるよね、
というボランティアの声から生まれた事業もあります。(千里地域での日本語交流活動の創出につながった)
(3)支援しすぎない支援を~ピアな立場での支援
子育て中の外国人ママを対象としたボランティアは、自身も子どもが小学生までの保護者が中心で、小学校を卒業したらその活動のボランティアも卒業することになっています。同じ状況だからこそ共感できることも多いし、支援しすぎて外国人の方の自主性を損なわないようにと出てきた仕組みです。
(4)主客逆転~助けていたつもりが、自分がエンパワメントされていた
外国人を助けているつもりが、活動の中で自分の抱える悩みやしんどさも受け止めてもらえる中で、日本人もエンパワメントされていきます。
(5)ネットワークの力で問題を解決する
1人の相談には、さまざまな課題が複合している場合が多々あります。
1つの機関だけで抱え込むのではなく、培ったネットワークの力を借りながら支援や事業が行われています。
4.事業による変化
(1)交流の中で相互理解が育まれています。
対等な関係づくりがあるからこそ、お互いの悩みを出し合える関係がつくられていきます。その中で、人間同士としての相互理解につながっています。
(2)外国人の居場所が地域の活性化につながっています。
外国人を中心に据えた場所があることにより、人が集まったり新しいアイデアが生まれたりなど、さまざまな磁場が生まれています。大切なことは、外国人「も」、地域で「安心」して生きる環境を整えるための視点です。
(3)プラス情報の発信者に
ボランティア活動などで学んだ人たちが、それを周囲に伝えることで外国人に関する情報がプラスな内容で伝えられていく機会が増えています。
5.課題や提言、展望
(1)双方向の営みがある事業づくり
①場づくり(安心できる居場所・仲間)
外国人(マイノリティ)の声を聴く場を確保することが必要です。そのことを、マイノリティの権利保障にもつなげていきます。
②人づくり
マイノリティの声に耳を傾け続けることで、日本人(マジョリティ)の意識の変革へとつなげていきます。
③お互いが必要としている部分でつながってwin-winな関係になるためには、日本人自身の学びの場にもなるような仕組みづくりが必要です。
(2)日本人(マジョリティ)側の学びほぐし
場づくり、人づくりその前提として、声にならない声に耳をかたむけ、身につけた既存の概念や考え方をいったんほどいていくことが大切になってきます。
(3)理念の継承
誰の何のための取組かがぶれないためにも、スタッフやボランティアの中で理念や事業を貫く哲学の共有と継承が大切になってきます。
地域に住むすべての人が差別や不利益を受けることなく、公正な社会であるべきだという理念。それを実現するためには、外国人だけが、行政だけが、がんばるのではなく、社会のおかしさに気づいた私たちこそが、周縁化されている人たちの権利保障を行う役割であるという自覚が必要になってきます。
(4)持続可能な活動のための協働
行政や民間団体含め、多機関との連携が必要となります。そのためにも、日常のネットワークづくりが大切になってきます。
(5)人と人が出会う場所づくり
知識だけを注入するより、出会い、友だちになり、そこから関係性を育むことで外国人問題への理解がより具体的に深まります。
(6)数珠繋ぎなクチコミネットワーク
外国人が国際交流協会の相談窓口や事業にアクセスできるきかっけは、知り合いからのクチコミの場合が少なくありません。
また、ここでのボランティア経験のある人たちのプラスの情報発信を含めたアナログなネットワークも大切にしていくことが必要です。
平成30(2018)年3月掲載