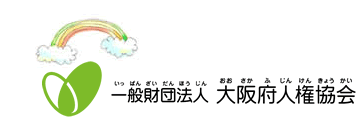|
|
代表理事 堀河 昌子 さん |
|
||
|
認定特定非営利活動法人大阪被害者支援アドボカシーセンターは、犯罪や事故に遭われた被害者やご家族に対して相談、支援、権利を擁護して代弁するというアドボカシー活動をおこなっています。 活動の始まりはH7(1995)年に起こった阪神淡路大震災の直後でした。それまで日本では「心のケア」に対する認識はほとんどありませんでしたが、この震災によって心身に大きなダメージを受けた人に対するケアに注目が集まるようになりました。当時、私は大阪YWCAで活動していました。前年に起きたロサンゼルス大地震を経験した人から「混乱が一段落すると心の問題が出てくる。心をケアする活動が必要だ」とアドバイスを受け、震災の10日後にはチームを組んで被災地に入りました。そして学校や公民館などに設置された避難所を中心に、被災した方々の話を聴かせてもらうという活動を始めたのです。 |
||
|
||
|
アドバイスされた通り、被災した方たちは時間が経つにつれて「助かった」という安堵感から、大きな災害に対してなす術もなかったという無力感や家族や居場所を失った喪失感にとらわれるようになりました。その人なりの言葉で大変な経験が言語化されていくのを、私たちは聴くことに徹するという姿勢で受け止めました。この「心のケアプロジェクト」に協力してくださったのが、全国に先駆けて「東京犯罪被害者相談室」を立ち上げておられた山上皓先生です。そのご縁で犯罪の被害に遭った人も支援を必要としていることを知り、H8(1996)年4月に民間被害者支援組織としては全国で3番目となる「大阪被害者相談室」を開設しました。 電話相談からスタートした活動でしたが、初年度から年間300件にのぼる相談があり、多くの人が支援を待っていたことを実感しました。ある女性は30年前の性的被害を話されました。心身にダメージを受け、人間関係もうまくいかないまま、誰にも言えずに生きてこられたのです。「やっと聴いてもらえるところができた」という言葉は今も忘れられません。
|
||
|
||
|
電話相談を中心に「心のケア」を意識して始まった活動でしたが、長く関わる人が増えるとともに「心のケアも大事だが、具体的にこれから自分はどうなるのかが不安だ」と言われることが増えてきました。「事情聴取を受けるのがしんどい」「裁判の傍聴に行きたい」など具体的な問題があると同時に、「被害者にも落ち度があったのでは」という社会の冷ややかなまなざしも被害者やご家族を苦しめます。 そこでH14(2002)年、自宅訪問や警察、病院などへの付き添い、裁判の代理傍聴など、より直接的な支援と被害者の権利擁護と代弁を目指して現在の形となりました。一方で私たちは「大阪府被害者支援会議」「全国被害者支援ネットワーク」に加盟するなど、多くの組織や人とゆるやかにつながりながら学びと経験を積み重ね、H13(2001)年には大阪府警察本部より「民間被害者相談員」の委嘱を受けました。犯罪被害者支援はとてもデリケートな個人情報を扱うため、民間組織として関わるにあたって壁を感じることが多々ありました。けれど支援を求めて連絡をくださるお一人おひとりに寄り添い続けることで、行政や警察などから信頼を得られたように思います。
|
||
|
現在は被害者支援員の養成や意識調査の実施、一般向けのフォーラム開催など啓発や調査もおこなっており、活動の幅は年々広がっています。しかしあくまで活動の軸足は「被害者支援」であり、その主体は被害を受けた当事者やそのご家族です。 日本の被害者支援の歴史とともに歩んできた活動のなか、私自身も多くのことを被害者やご家族のみなさんから学んできました。この活動に関わるまで犯罪事件は新聞やテレビで接するだけで、他人事でした。それは被害を受けた方たちも同じで、みなさん「まさか自分が」と言われます。誰もが「被害者」になる可能性があるという現実をつくづくと思い知りました。 被害を受けた人は心身に大きなダメージを受けますが、やがてその人なりの回復の道を歩んでいかれます。「同じ思いをもう誰にもさせたくない」と社会に向けて活動される方もいます。私たちも自助グループの活動を支援させていただいています。 回復の道のりも時間もそれぞれですが、少なくとも10年スパンでの見守り、サポートが必要だと感じています。たとえば何年たっても事件のあった日が近づくと感情が揺れる方がいます。こういう方に必要とされる時にはいつでもお話を聴ける態勢でありたいと考えています。 支援する側として大切なのは、「何かしてあげたい」「役に立たなければならない」という意識をもたないこと。私たちに連絡をとってこられること自体、その方の心のなかに「何とかしたい」という気持ちがあるのです。その第一歩をしっかり受け止め、長い回復の道のりにそっと寄り添っていくのが私たちの役割です。ダメージを抱えつつ、どう生きていくか。その答えも生きていく力も、それぞれが持っているということも当事者のみなさんから教えていただきました。 H28(2016)年2月掲載
|