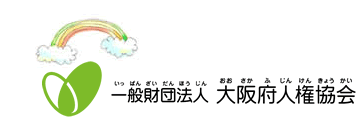第3回相談事業研究集会を開催しました
2012年2月9日(木)13:30~17:00 HRCビル(大阪市港区)において「第3回相談事業研究集会」を当協会主催で開催し、市町村人権協会、人権地域協議会をはじめ社会福祉協議会、就労支援等の各地域の相談員ら102名が集いました。
はじめに、内閣府パーソナル・サポート・サービス検討委員会委員でもあり、大阪市立大学大学院生活科学研究科教授の岩間伸之さんから『「パーソナル・サポート・サービス」が意味するもの~個別的・包括的継続的支援の重要性~』というテーマで講演をいただきました。パーソナル・サポート・サービス(以下PSP)の意味するものは、制度にひとを合わせるのではなく、十人十色のオーダーメイドによる個別支援を伴走型で行うこと。就労自立までの距離のある人たち=すべての人を対象とする支援事業ということ。支援のプロセスそのものを重視した支援であること。そのために各団体やひととの連携と協働による支援体制の構築が不可欠であることなどPSPについてより理解を深めるためのポイントや理念、ソーシャルワークについて丁寧にお話をいただきました。
基調講演を踏まえて、ふたつの地域より実践報告をいただきました。特定非営利活動法人暮らしづくりネットワーク北芝の池谷啓介さんからは、「ひとと組織のネットワーク」をテーマに、どのようなネットワークを構築し、支援を行ってきたのか実践報告をいただきました。ネットワークとは単に相談先を紹介するのではなく、各組織や個人、地域住民も含めてそれぞれのもつ力を十分に発揮できるように「仕込み」を意識することが重要な視点であるとお話しいただいたことが印象的でした。
また、一般財団法人八尾市人権協会の笠原辰司さんからは、「早期発見と継続支援の重要性」をテーマに地域の拠点としての取り組みを紹介いただきました。早期発見のためにはネットワークの構築と継続が重要であること。また、相談者との信頼関係の構築と相談者自身が次のスッテップに向けて自己認知できる支援と自己決定を重視した継続的な支援についてお話しいただきました。
その後参加者も含めたディスカッションで議論を深めていきました。
特定の機関や特定の相談員が相談支援を進めていくのではなく、地域の関係者がネットワークを組みながら地域全体で展開していくことが重要で、従来の「福祉」の枠から脱却し、地域における新しい支援のありかたを創造することを確認しました。また、今日からの相談支援活動に力をもらった研究集会になったと思います。