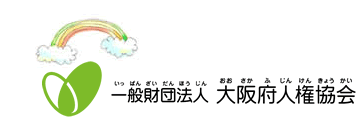子どもを中心にすえた権利や法律の見方・活用を学ぶ
~「児童養護施設や里親をめぐる法的諸問題の学習会」を開催しました~
児童養護施設や里親といった社会的養護において、関係する法律を学び、よりよい支援のためにできることについて考える学習会を、2011年3月23日に箕面市立萱野中央人権文化センターで開催しました。弁護士であり、CVV*スタッフでもある森本志磨子さんを講師に、児童養護施設の職員の方、里親の方、人権文化センター、人権地域協議会やNPO関係の方など28人の方にご参加をいただきました。
*CVV…児童養護施設でいま生活している子どもたちや、生活したことのある若者たちの居場所づくりを目標に活動する団体
学習会は、事前に参加者からいただいていた質問への答えを織り込みながら進められました。参加者からは、里親の元で育つ子どもの名前について、通称(里親の名前)と本名(戸籍名)の使用について、法律上どこまで通称名の使用が可能か、就職等の身元保証の問題、携帯電話や賃貸住宅や奨学金などのローンといった契約に関する問題などといった質問が出され、それにも答えながら進められました。
講師から話された具体的内容は、子どもが児童養護施設や里親の元で育つに至る経緯や、入所後の養育における法的裏づけ。社会的養護が児童福祉法を中心に憲法や民法など国内法や、子どもの権利条約といった国際条約にいかに位置づけられているかという説明。また、子どもの権利擁護のためのシステム、親権、養親、未成年後見、里親、子どもの面会権、子どもの養育請求権などに関連する問題が詳しく紹介されました。
講師の言葉として、「子どもは発達する権利がある」「自分が権利(人権)の主体、という意識を持つ子どもに育てるのが施設や里親であり、それで初めて互いが対等な関係になれる」ということが印象的でした。
法的な知識とともに、子どもは人権を持つ主体として尊重されるべき存在であり、社会的養護はだれのために行われているものなのか、といったあたり前の基本をもう一度考えさせられる時間となりました。
 |
 |
【参加者の感想】
●現場ではどうしても法律とリンクさせる部分が少ないが子どもの権利をしっかりと考える上では、現場職員も少こしくらいの子どもにかかわる法律をしっておくことも大切なのだと知った。難しいイメージがあるが、とても分かりやすくて良かった。
●子どもを中心に考えた法律の見方が参考になった。