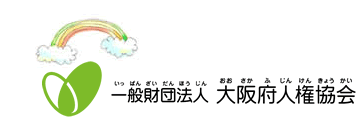「発見」「つなぐ」「支える」
相談事業の重要性を考える
「第2回相談事業研究集会」を開催しました
2011年3月24日(木)、午後1時~ 大阪市立中央会館において「第2回相談事業研究集会」を当協会主催で開催しました。地域の相談員ら65名が集いました。神尾理事長の開会挨拶のあと、内閣府パーソナルサポートサービス検討委員でもあり、特定非営利活動法人北九州ホームレス支援機構・ホームレス支援全国ネットワークの理事長の奥田知志さんから「絆の制度化・持続性のある伴走型コーディネート」というテーマで講演をいただきました。「絆(家族)を失った新しい困窮に対しては出会いから看取りまでの人生の支援が必要。人を支援するのは人であり、支援を受けた本人が誰かの絆になるという関係づくりをしていきたい」と語りかけられました。また、東北関東大震災の被災者支援にいち早く取り組まれ、北九州市では官民の共同事業として、被災者の一時的避難の場所として、新たな出発の場所とする「第2のふるさと」計画を提案・発表されています。
引き続き開催したシンポジウムでは、「地域で支える相談事業を考える」をテーマに、当協会の谷川理事のコーディネートのもと、パネリスト4名の方からの発題をいただきました。豊中市社会福祉協議会の勝部麗子さんからは、CSW(コミュニティソーシャルワーカー)の活動を通じ「セーフティネットの課題-地域力と開発力」の提起があり、一人暮らし高齢者のひきこもりの支援やホームレス支援等の具体事例を交えて話しをいただきました。
特定非営利活動法人暮らしづくりネットワーク北芝の井原芳朗さんからは、箕面市で運営されていた、萱野中央人権文化センター(愛称:らいとぴあ21)の指定管理を受託し、それまでの地域のネットワークや活動を生かし、地域の拠点としての取り組みを紹介いただき、隣保事業士の内山三重子さんからは、柔軟なよりそい型支援の相談事例を紹介いただきました。
また、行政の立場から、河内長野市人権推進室の中野卓見さんからは、市民からの人権相談をワンストップで行えるよう、庁内の関係機関はもちろんのこと、市内の当事者団体、関係団体等と連携・ネットワークを組んで、行政の縦割りを排し、市民サービスに努めているお話しをいただきました。
今回、それぞれからの発題の中で、発見されにくい地域課題や複雑で複層する課題を、いかに地域の社会資源を活用し、また、行政機関やさまざまな団体とのネットワークを持ちながら、当事者によりそい、継続的に取り組みをすすめていくことが必要で、そのための地域づくりがとても大切であることを再確認した集会でした。