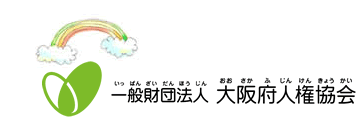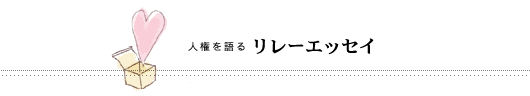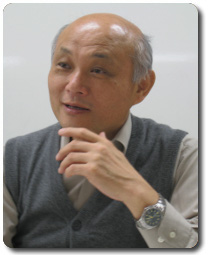 |
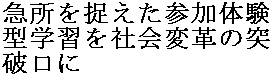 森 実(もり みのる)さん 大阪教育大学教職教育研究開発センター教授
|
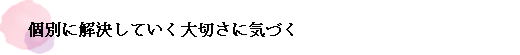 |
|
大学で部落問題や同和教育を教えるのがおもな仕事です。だから、「ぼくほど部落問題学習について長い時間考えている教員はあまりいないのでは」とときどき思います。中身の深さじゃなくて時間の長さだけですよ。それなのに授業はうまくいかない。今でもそうですが、1984年に大阪教育大学に就職した当時は悩みました。夜中の3時までかかって教材研究をしたのに、講義すると学生たちはしゃべったり居眠りしたり。一生懸命やればやるほど学生の態度はひどくなる感じ。悪循環でした。
発想の転換になったひとつは、ある結婚差別の事例を学んだことです。男性が部落出身者であることを理由に結婚を猛反対されたカップルが、男性の先輩に相談しました。するとその先輩は「一番危ないのは座敷牢のようなところに閉じこめられて、家族や親戚に入れ替わり立ち替わり、泣き落としや脅しをかけられることだ。座敷牢状態になることだけは避けて、短くてもいいから毎日会える時間をつくれ」とアドバイスしたといいます。それを聞いて、「なるほど!」と思いました。結婚差別を乗り越える急所のひとつは、座敷牢状態を避けることなのだ。 改めて振り返ってみると、ぼくは、「社会体制を変えれば差別はなくなる」「個別の問題は決意で乗りきれる」と考えていました。だから社会を変えるために何が必要なのかを一所懸命に伝えようとしていました。しかし、一つひとつの問題の急所を徹底して洗い出し、戦略を考えて解決していくことも重要ではないかと思うようになったのです。 |
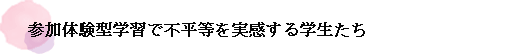 |
|
そこで授業の進め方を根本的に考え直しました。まず、学生時代に社会教育を学んで知っていたロールプレイをやってみました。本や講義で学べる知識と、実際の対人関係で使えるスキルにはズレがあります。そのズレの自覚を通して実践力を養いたかった。これに手応えを感じて、「Z市の雇用実態調査」と「貿易ゲーム」というプログラムを取り入れるようになりました。「Z市」は、会社の採用基準を判断するシミュレーション学習です。これを通じて、何が差別で何が平等なのかを自分たちは案外わかっていないことに気づきます。「貿易ゲーム」は、紙(資源)や道具(技術)を不平等に与えられたいくつかのグループの間で、どれだけ多くの富を築くかを競います。「Z市」は「機会の平等」だけが平等ではないと理屈で理解するのがねらいです。一方、「貿易ゲーム」は「機会の平等」が達成されている社会で何が起こるかを実際に体験し実感することがねらいです。「貿易ゲーム」をすると、学生たちは熱中し、いろいろな感想を発表します。「機会の平等」の不平等性を実感するのにはとてもいい教材だと思います。
授業でロールプレイを始めた80年代後半にはまだ参加体験型学習という言葉も知りませんでした。ただ、社会教育や学生運動を通じて、教育の主体は学習者であることや、学習者が興味を示さないのは教える側の問題だという意識はありました。 |
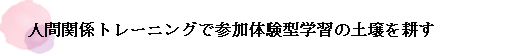 |
|
90年代に入り、日本でも参加体験型学習が取り組まれるようになりました。95年から「人権教育のための国連10年」が始まると知り、これはチャンスだと思いました。「○○の10年」は、悪くすると頭の上を通り過ぎるだけに終わります。だから、それで終わらないよう、これをきっかけに教育の現場が変わるようなことをしたい。まずは参加体験型学習を定着させようと『今、人権教育が変わる』というブックレットもつくりました。
その後、参加型学習はずいぶん定着しました。ただ、普及したのは、全体としては「人間関係トレーニング」の色合いが濃く、部落問題学習はまだまだです。それで、「方向が違う」と物足りない気持ちがあったのも事実です。 しかしつい最近、その思いが少し変わってきました。転機は、いくつかの学校で参加体験型の手法を使って人間関係のトレーニングをし、結果的に子どもたちが落ち着いたなどの成果があったと知ったことです。その話を聞き、人間関係トレーニングが参加体験型人権学習をさらに広めるために役立つのではないかと思いました。人間関係づくりは教員のニーズが高い分野ですから、そこで参加体験型学習の効果が認められ、どの学校でもおこなわれるようになれば、先生たちは参加型学習の手法に習熟し、子どもたちも慣れます。そのうえで部落問題学習を参加体験型でおこなえば、スムーズに受け止められるでしょう。学びの土壌を耕すというイメージです。 |
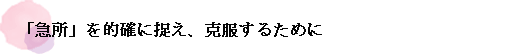 |
|
参加体験型による人権問題学習を進めるには「認識や行動を阻んでいる急所は何かを明確にさせ、どんなアプローチができるかを考える」ことが求められます。「急所」は具体的であればあるほどいい。 (2010年12月掲載) |
同和教育・人権教育・識字教育・社会教育などを専攻。大学では、部落問題概論や人権教育論などを担当。部落問題をはじめ、さまざまな社会的・政治的な課題を個々人が自らの問題として考えるようになるプロセスに関心を持つ。
おもな著書に『「教室の人権教育」何が実践課題か』(明治図書)、共著に『同和教育への招待』(解放出版社)、編著に『同和教育実践がひらく人権教育-熱と光にみちびかれて』(解放出版社)、共編著に『シリーズ解放教育の争点』(明治図書)などがある。 |
||