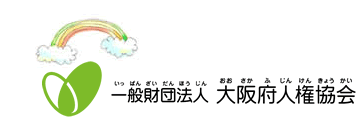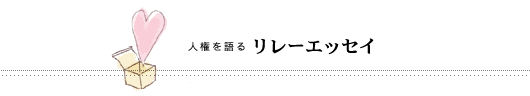|
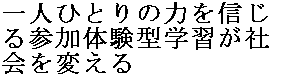 栗本 敦子(くりもと・あつこ)さん ファシリテーター
|
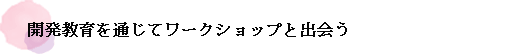 |
|
あるテーマについて学んだり話し合ったりする時、参加者の自発的な発言を通して議論を深めていく「ワークショップ(参加体験型学習)」という方法があります。わたしが仕事としているファシリテーターは、ワークショップで、メンバーが参加しやすく、議論が深まるような場をつくるよう全体を調整する役割を担います。 |
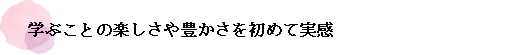 |
|
ゲームという形で出会った参加体験型学習でしたが、わたし自身が大きな影響を受けたのは、ブラジルの教育者、パウロ・フレイレの理念に共感した人たちがおこなうワークショップでした。たんなる手法やハウツーではなく、参加ということを大事にする姿勢、参加者の力に対する信頼を学びました。もうひとつ影響を受けたのは、開発教育が盛んだったイギリスでおこなわれていたワールド・スタディーズという取り組みです。相互依存を深めていく世界について学ぶためのプログラムで、教師向けのハンドブックの冒頭には「わたしは問いかけつつ教えているか」といったチェックリストがありました。学ぶ側ではなく、教える側の姿勢を問う考え方に強いインパクトを受けました。 |
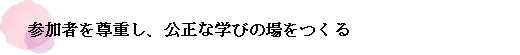 |
|
人権教育には4つの側面があるといわれています。「人権のための教育(Education FOR Human Rights )、「人権としての教育(Education AS Human Right)」、「人権を通しての教育(Education THROUGH Human Rights )」、「人権についての教育(Education ABOUT Human right)」です。これまでの人権教育は圧倒的に「人権についての教育」でした。いっぽうで、ワークショップは" FOR "「人権のための教育」であり、" THROUGH "すなわち「学習過程そのものも人権が守られた状態で展開されるべき」だという側面がとても強いと感じています。” THROUGH "とは、学んでいる場がまさに人権尊重が体現されている場であるということです。もちろん優れた講義もあると思いますが、参加体験型はめざすものと学ぶ場のあり方が一致していてとても効果的だ、というのがわたしの考え方です。 |
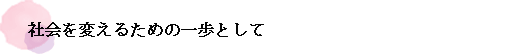 |
|
ファシリテーターとは、答えをもっている人ではなく、その場にいる人たちとともに考えるための問いをたてることを役割とします。その場で明確な「気づき」に至ることは求めません。ざらっとした違和感や、もやもやした気持ちを持って帰ってもらい、ある時、家庭や職場で「あ、この前のワークショップで出ていた話と同じやわ」と感じてくれれば大成功なのです。 (2010年10月掲載) |