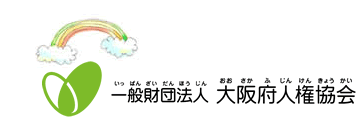"参加型で学ぶ"人権・部落問題学習を考える研究会を開催しました。
人権・部落問題学習を参加体験型学習で行うプログラムを検討する機会として、「"参加型で学ぶ"人権・部落問題学習を考える研究会」を2010年2月6日(参加者23人)と3月15日(参加者24人)に開催しました。
大阪府人権協会では、この夏に開催する「人権・部落問題学習のファシリテーター養成講座」に向けプログラム開発に取り組んでおり、この研究会は、その一環として開催しました。
2月6日の研究会1では、"部落問題"を学ぶプログラムを取り上げました。内容は、「部落問題との出会い直し」をキーワードにして、 Facilitator's LABO(えふらぼ)の栗本敦子さんに。「忌避、権力関係」をキーワードに大阪教育大学の森実さんに講師をお願いし、参加者とその内容を検討しました。
3月15日の研究会2では、"人間関係"と"人権概念"を学ぶプログラムを取り上げました。内容は、「情報、コミュニケーション、ステレオタイプ」をキー ワードに、八尾じんけん楽習塾の大谷眞砂子さんに。「構造的差別、選択、社会への関わり」をキーワードに栗本敦子さんに講師をお願いし、参加者とその内容 を検討しました。

大阪府人権協会では、この夏に開催する「人権・部落問題学習のファシリテーター養成講座」に向けプログラム開発に取り組んでおり、この研究会は、その一環として開催しました。
2月6日の研究会1では、"部落問題"を学ぶプログラムを取り上げました。内容は、「部落問題との出会い直し」をキーワードにして、 Facilitator's LABO(えふらぼ)の栗本敦子さんに。「忌避、権力関係」をキーワードに大阪教育大学の森実さんに講師をお願いし、参加者とその内容を検討しました。
3月15日の研究会2では、"人間関係"と"人権概念"を学ぶプログラムを取り上げました。内容は、「情報、コミュニケーション、ステレオタイプ」をキー ワードに、八尾じんけん楽習塾の大谷眞砂子さんに。「構造的差別、選択、社会への関わり」をキーワードに栗本敦子さんに講師をお願いし、参加者とその内容 を検討しました。
| 参加者の方からは、 | |
| ■ | クイズ形式でとても参加しやすく、楽しいだけでなく、ヘェーと思うことも学べてすごく良かったです。実際、使ってみたいと思えました。 |
| ■ | 「差 別」をテーマにワークするのは、「答え」がすっきり出るものではないので、とても難しいと思いました。ただ、「現実に差別がある社会だ」というところから スタートして→社会の仕組みから変えていく→そのためには、個人でも何かしなければならないという事がわかりました。 |
| といった感想をいただきました。 | |