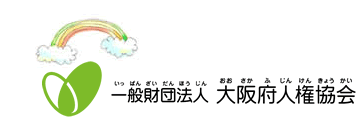|
地域における共通の課題解決のために、被差別・社会的マイノリティ当事者と住民とが協働で取り組むコミュニティづくりを応援するために、2009年度より「コミュニティづくり協働モデル支援事業助成金」を実施しています。この助成金を活用して、2009年度は9の団体による事業が行なわれました。この活動を発表し交流することと、来年度の助成金の説明のために、2010年3月13日、大阪人権センターにおいて、40名の参加で「人権のコミュニティづくり交流会を開催しました。
第1部は、助成団体からの活動発表で、次の事業がそれぞれの団体から発表されました。
①Mishima“いきいき・元気”応援プロジェクト
茨木市人権三島地域協議会 |
②ALL人権ツアー食文化事業
特定非営利活動法人ヒューマンライツ・アドバンス・堺 |
③ハンセン病回復者との交流を深め、世代をつなぐ記録づくりを進める
みんなでつくる学校とれぶりんか |
④子どもふれあいコミュニティプラン
泉佐野市人権を守る市民の会長南小学校区地区委員会 |
⑤電動車椅子講習「外へ出よう!街へ出よう!」
特定非営利活動法人障害者自立生活センター・スクラム |
⑥セクシュアル・マイノリティのライフプランと法制度
G-FRONT関西 |
⑦エスニックマイノリティの地域ネットワークづくり事業
特定非営利活動法人トッカビ |
⑧母語保持育成プログラムづくり事業
大阪府在日外国人教育研究協議会 |
⑨地域で「ふれあい」「おもいやり」「たすけあい」運動
特定非営利活動法人NPOスバル |
これを受けて、事業推進委員からのコメントが行なわれました。
田村太郎さん(特定非営利活動法人多文化共生センター・大阪代表)からはビデオメッセージで、①課題への視野を広げる、②効果の持続性を広げる、③協働のパートナーを広げること。冨田めぐみさん(社会福祉法人大阪府総合福祉協会)からは、地域の課題に気づかれて取り組まれていることはすばらしい、これを地域での協働として育てていくことを追求したい。高田一宏さん(兵庫県立大学)からは、①人権課題が多様化、複雑化している、②コミュニティづくりには様々な担い手がある、③子どもや若い世代の感性や発想が柔軟で面白い取り組みにつながる。推進委員会座長の奥田均さん(近畿大学)からは、①コミュニティづくり協働モデル支援事業ができた背景には、被差別・マイノリティの人たちとの協働によって忌避意識が克服されることがわかったことがある、②差別は孤立を生むのでつながりやネットワークづくりが必要になる、③今後は事業経営という視点から持続可能性を追求してほしい、などと語られました。
第2部は2010年度助成金の説明で、募集案内の内容と4月からの募集予定が説明されました。この交流会を終えて、人権のコミュニティづくりをさらに広げていくことが求められています。
なお、助成団体の活動報告書は、別途掲載します。
|