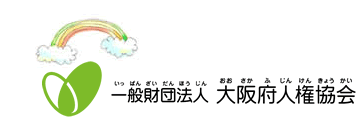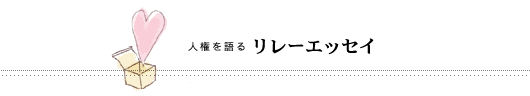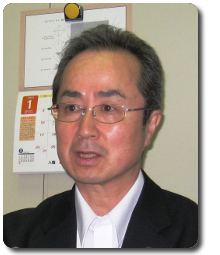 |
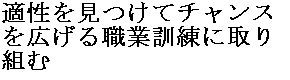 高見一夫(たかみ かずお) さん (A´ワーク創造館(大阪地域職業訓練センター)館長
|
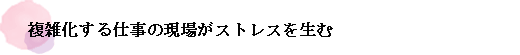 |
|
今、仕事をめぐる状況は非常に複雑化しています。高度経済成長期のように求人も条件も右肩上がりという状況とは一変し、求人が絞られるうえに、仕事の内容も複雑で多様化し、しかも変化が激しくなっています。たとえば以前は単能工といって一人ひとりが担当する仕事をもっていました。しかし今は多能工化が進み、一人で幅広い仕事ができることを求められます。急激な経済の変化の中では、これは企業にとっては当然の要求です。ひとつの仕事しかできない人よりも、さまざまな仕事ができる人を雇うほうがコストを抑えられるからです。しかし働く人には大きなストレスがかかります。そのうえ成果主義、能力主義となれば、同僚も仲間ではなくライバルです。近年、うつ病になる人が増えているのも無理はありません。 |
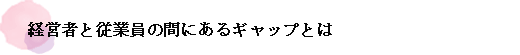 |
|
(株)野村総合研究所の「若年労働者活用実態に関するアンケート調査」(2005年)によると、自社の従業員のスキルに満足している企業経営者は2,3割にとどまっています。また、規模の小さい会社ほど満足度が低くなっています。一方で、採用時には熱意や責任感、人間性を重視する傾向がみられます。つまり、企業は熱意や人間性を見込んで採用しますが、いったん入社した人に対しては専門スキルや資格、課題解決能力など非常にグレードアップした能力を求めているのです。経済のグローバル化が進むなか、企業には以前のように時間をかけて新入社員を育てていくだけの余裕がありません。しかし従業員にはスキルアップを求めたい。こうした経営者の思いと従業員の実際のスキルというギャップを埋める職業訓練を提供する場が必要です。 |
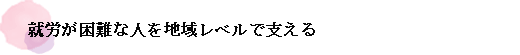 |
|
ニートやひきこもり状態にある若者に対する支援もおこなっています。たとえば、「これから学級」という講座では、なかなか就職に結びつかない人たちがコミュニケーション力をつけ、仲間づくりができる内容にしています。講座を卒業した人は、大阪市平野区の商店街に拓いたリサイクルショップ「ねこまる」を企画運営してもらいます。ささやかなコミュニティビジネスですが、接客やお金の管理などの経験によって自信が生まれます。なかには就職につながった人もいます。このように、カリキュラムを修了した後も自主的な集まりにスタッフが参加しています。 |
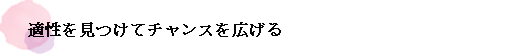 |
|
失業率はあがる一方ですが、決して仕事がないわけではありません。働きたい人と仕事とをマッチングさせるためのコーディネイトがないのだと私は考えています。「働く力」を養ったり職業訓練を受けたりする場も十分ではありません。スキルだけの職業訓練なら通信教育でもできますが、本当の意味での職業訓練とは、自分のことをきちんと話せて、相手の話も聞くことができること。そして講師とコミュニケーションがとれ、若干のスキルアップをして元気になって卒業していくことです。就職が困難な人だけに注目をしていると、「挨拶ができるか」「通勤できるか」などと最初からハードルを設け、「あれもこれもしなさい」と追いつめてしまいがちです。そうではなく、その人ができることを見つけ、それをきっかけにチャンスを広げられるよう支援することが大切です。 (財団法人大阪府人権協会は、A´ワーク創造館を運営する有限責任事業組合大阪職業教育協働機構に参画しています。) |