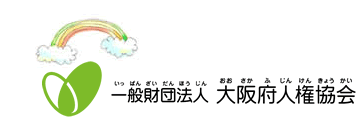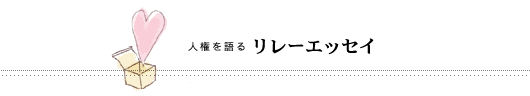|
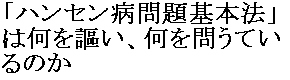 神谷 誠人(かみや・まこと)さん 弁護士
|
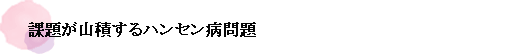 |
|
1998年、ハンセン病の回復者の方々が原告となり、国家賠償を求める裁判が熊本地裁で起こされました。翌年には東京と岡山でも同様の提訴がおこなわれました。私は主に岡山で提訴された「瀬戸内ハンセン病訴訟」の弁護団の一員として、ハンセン病問題に関わってきました。 |
 |
|
「『らい』予防法廃止法」とは、予防法が廃止になり、隔離政策から開放政策へと転換された後も療養所にとどまらざるをえない回復者の方の生活を保障するというものです。長年の隔離政策や偏見・差別によって、社会生活の基盤がなく、家族をはじめとする人間関係が断絶された状態ではなかなか退所できません。実際、予防法廃止後に退所した人は全国で18名でした。そのため、廃止法によって入所者のみなさんの生活を保障することが必要だったのですが、逆に療養所を入所者のみの利用に限定したため、療養所内の医療施設や介護機能を地域の人だけでなく、退所された方も利用できないということになりました。また、地域社会との円滑な交流がなければ、療養所はいつまでも社会から隔絶された場所であり続けるという問題意識からも、新たな法律が必要だという議論が高まり、2007年7月から法律の制定を目指して署名活動が始まりました。約半年で93万人筆もの署名をいただき、2008年6月に国会のほぼ全会一致で「ハンセン病問題基本法」が成立しました。 |
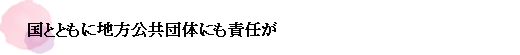 |
|
基本法の趣旨、目的は「ハンセン病回復者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むための基盤整備をおこなうこと」と、「ハンセン病回復者等に対する偏見と差別のない社会の実現」です。具体的な施策は法3条に掲げられた3つの理念を前提におこなわれます。1つは、ハンセン病問題に対する施策は、「隔離政策による被害の回復」としておこなわれることです。被害の回復とは、権利の回復でもあります。決して国が勝手にやったりやらなかったり、あるいはやってきたことを変えたりしてはならないということが謳われています。2つめは、入所者が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができるよう配慮する責務があるということです。「豊か」とは抽象的ですが、人間として生活できるだけの質を維持した生活を確保されなければならないということです。最後に、ハンセン病に罹患していた、あるいは罹患していることを理由にして差別などをしてはならないという、差別禁止条項が挙げられています。 |
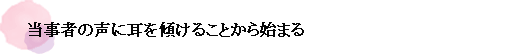 |
|
基本法では、当事者の意志が十分に尊重されなければならない、とされています。ハンセン病問題の施策が権利と被害の回復である以上、権利の主体である当事者の意志が反映されなければ、本当の意味での回復にはならないからです。 |