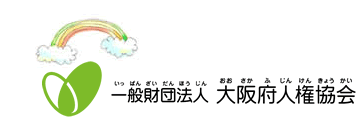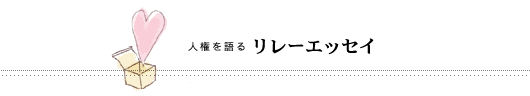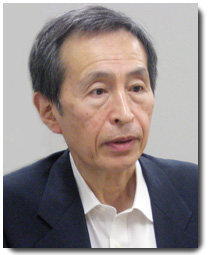 |
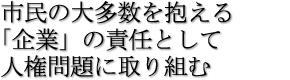 内海 義春(うつみ・よしはる)さん 大阪企業人権協議会 事務局長 |
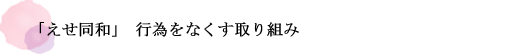 |
|
私たちの活動のひとつとして、電話相談を受け付けています。そのなかには「えせ同和」に関する相談があります。事例としては、「電話がかかってきて同和問題の本を買うように言われたり、勝手に送りつけられたりした。どうすればいいのか」というものがほとんどです。その際にまず出てくるのが、「これは、えせ同和ですか」という質問です。実はここが重要なポイントなのです。「“真っ当な”運動団体が言ってきたのであれば、買うのですか」ということです。つまり、「えせ」であろうとなかろうと、必要なければ買わなければいいのです。はっきりと断れない背景・根っこには、「“真っ当”な運動団体に断って、後で差別だと騒がれたら大変だ」など、「同和地区の人は怖い」というステレオタイプ・偏見が垣間見られます。もちろん具体的なアドバイスもしますが、「必要ないからと断っても部落差別にはならないでしょう。なぜはっきりと断れないのかというところを少し考えてくださいね」と付け加えます。マニュアル的な対処法だけでは、「えせ同和」行為をなくすことにはなりません。「えせ同和」問題を正しく理解するには、「人権の視点」が欠かせないのです。 |
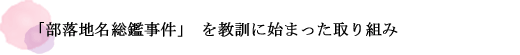 |
|
「部落地名総鑑事件」(1975年)が発覚したのを契機に、1977年に「企業内同和問題研修推進員(現在は公正採用選考人権啓発推進員)」制度が定められました。社員数100名(大阪は25名)以上の事業所において、適正な採用選考システムの確立等に中心的な役割を果たす担当者を設置するというものです。一方で、大阪府内では1976年頃から、企業による自主的な人権啓発組織が設置されるようになりました。地名総鑑事件に限らず、当時の企業には差別的な体質があるとの自覚と反省から生まれた取り組みです。行政の指導によってつくられた制度と企業の自主的な取り組みが結びつき、大阪府内の各市町村で企業連絡会(地域連絡会)が組織されるようになりました。そして1981年、これらの連絡会が互いに連携し、幅広い啓発活動を展開するために「大阪企業同和問題推進連絡協議会(大阪企同連)」が設立されました。現在の大阪企業人権協議会の前身です。 |
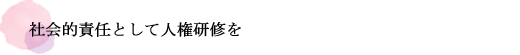 |
|
設立の経緯もあり、取り組みの大きな柱は「公正な採用選考」です。数年前まで全般的に採用が抑えられ、同時に「公正な採用」という意識が薄れる傾向が見られました。そこで原点に立ち返ろうと、公正採用選考人権啓発推進員現任者研修会の研修プログラムに、公正採用に関する実務的な講座を組み入れるなどの取り組みを進めています。 |
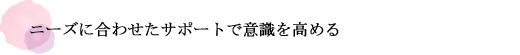 |
|
かつては「啓発をしましょう、しなさい」と、いわば“号令”をかけることに力を入れていました。しかしそれでは「やらなければいけないことはわかっているけど、具体的にどうすればいいのかわからない」という企業はなかなか動けません。そこで、私たちはまず「企業が社内人権研修をすることは、企業の社会的責任(CSR) としての具体的な取り組みのひとつである」と明確に宣言しました。当たり前のことなのですが、これまでCSRの中ではなかなか言われなかったことです。そのうえで、「おおさか社内人権研修サポートセンター」を設立しました。研修のプログラムに関する相談や講師の紹介、人権研修リーダー養成のお手伝いなどをします。講師は、企業で人権を担当していた経験者から専門家まで、ニーズに合わせて紹介、派遣します。 |