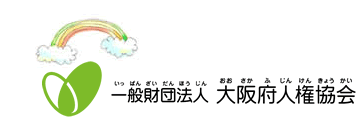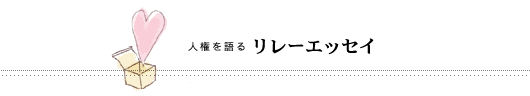|
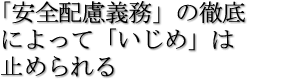 大沢 秀明(おおさわ・ひであき)さん 全国いじめ被害者の会 会長 |
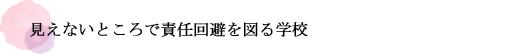 |
|
1996年1月22日。私の息子、秀猛は15歳で自ら命を絶ちました。いつもニコニコして、3人の兄たちにかわいがられ、母親の手伝いもよくしていた、やさしい息子でした。自殺をするなど、思いもよりませんでした。遺書を読み、初めて息子がいじめられていたのを知ったのです。「お父さん、お母さん、ごめんなさい」で始まる遺書には、中学校の入学式の日から始まったいじめについて書かれていました。殴られ続け、大切にしていたファミコンを脅し取られ、総額30万円ものお金も脅し取られていたのです。私は怒りで全身が震えました。 |
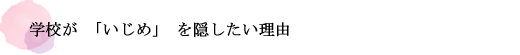 |
|
学校の思惑が見えてくると、私の怒りと不信は一層強まりました。しかし、自分なりに調べるうちに、だんだん学校側の「事情」も見えてきたのです。学校には処罰賠償責任というものがあり、学校内で事件や事故が起きると都道府県の教育長から市町村の教育委員長、校長、教頭そして担任まで責任をとらねばなりません。たとえば、現場の教師が「いじめ」の存在を認めると、上司である校長や教頭のみならず市町村や都道府県のトップまでが責任を問われる。ですから、学校としては絶対に「いじめ」の存在を認めたくないわけです。 |
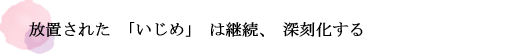 |
|
からかいやふざけ、いじめが発生した時、多くの学校は「いじめ」ではなく「トラブル」ととらえ、加害児童・生徒と被害児童・生徒を同時に呼び、「仲よくしなさい」と「指導」します。これでは「いじめ」を擁護したのも同然です。そして、「擁護」された「いじめ」は継続し、深刻化していきます。いじめられた子どもは教師への信頼をなくし、“仕返し”を恐れて「いじめ」を受けても教師へ訴えなくなります。その結果、被害を受けた子どもは「不登校」になったり、「自殺」を図ったりします。すると学校は、「いじめ」をなかったことにするため、今度は「家庭の問題」や「自殺した生徒の問題」にすり替えてしまいます。秀猛の時もまさにそうでした。「家庭に問題があった」「友だちとうまくコミュニケーションがとれなかった」などと言われ、遺族は子どもを亡くした悲しみに加えて大変な苦しみを味わいます。 |
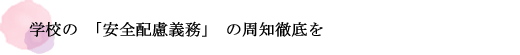 |
|
「いじめ」はこれからも起きるでしょう。重要なのは、「いじめ」を継続、深刻化させないことです。そのためには、常日頃から子どもたちに「いじめは決して許されない」と教えること、そして、「いじめ」の訴えがあれば事実を確認し、「いじめ」だと判断した場合は子どもたちの前でいじめた児童・生徒を厳しく指導することです。そうした姿勢があればこそ、子どもたちは「いじめがあれば先生が助けてくれる」と安心し、「いじめ」を訴えてくるのです。 |