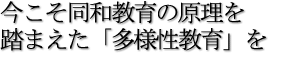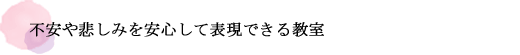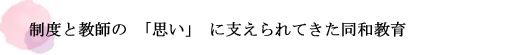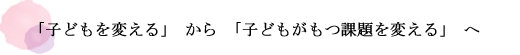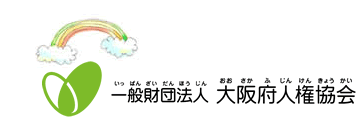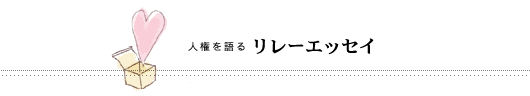|
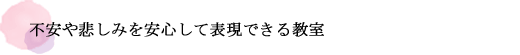 |
大学院生だった20代半ばから、ずっと大阪府内にある被差別部落に住んでいます。最初の1年間は同和教育の研究のために小学校の現場に入らせてもらい、1年生を中心にさまざまな教育活動を見せてもらいました。たとえば、朝食を食べていない子に対する欠食対策がありました。それは同和対策事業の一環です。朝食を食べていない子は体に力が入らず、勉強どころではありません。そこで毎朝、教員が朝食抜きの子どもの人数を確認し、パンと飲み物を買いに行き、1時間目終了後の休み時間に食べさせるのです。ただ食べさせるのではなく、「うちの人、ご飯つくってくれへんかったんか」「うん」「せやけど冷蔵庫のなかには卵があるやろ。今度、先生が卵焼きの作り方を教えてあげるから、自分でつくってごらん」という会話が交わされました。子ども自身が生活力を身につけていくような指導がなされていたのです。
また、ある朝のことです。朝の会が始まると、待ちかねたように「先生、あのな、うちのお父ちゃんとお母ちゃん、昨日の夜にケンカしよってん。おかあちゃん、殴られて出て行ってん」と話し始めた子どもがいました。教員は「そうか、そうか」と聞き、「他の子はどうや?」と子どもたちに尋ねました。すると「うちもそうや」と次々に声が挙がりました。最初に発言した子どもには、「ここでは何を話しても受け入れてくれる」という安心感があったのでしょう。そしてこうした発言によって、他の子どもも押し込めようとしていた気持ちを出せたのでしょう。教室は、不安や悲しみを安心して出し合える場となっていました。
|
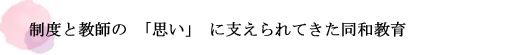 |
これらはほんの一例ですが、同和教育の原理といえると思います。部落に限らず、朝食を食べずに登校する子どもたちは今もいます。また、さまざまな事情によって親が子どもをじゅうぶんみてやれない家庭も少なくありません。
今、同和教育に対して、「特別扱いだ」などと批判する声があります。しかしいろいろな意味で厳しい状況にある親が多い今だからこそ、同和教育の精神と制度を全体化し、子ども同士がつながることのできる教育をさらに広げる必要があるのではないでしょうか。
もちろん、制度があっても教師の「思い」がなければ、せっかくの制度も生かされません。逆に「思い」があっても制度がなければ実際に働きかけるのは難しい。制度と「思い」があったうえでの同和教育なのです。そのことを当時の学校での様子を通じて学ばせてもらったことは、教育を考えるうえでとても大きなことでした。残念なことに、同和教育のそうしたソーシャルワーク的な面はあまり知られていません。
|
 |
一方、大学で授業をしていると、同和教育によい印象を抱いている学生があまりいないのを痛感します。校区に同和地区を含んでいる学校では、「思い」のある教員たちが制度を生かして組織的に取り組み、それなりの成果がありました。しかし校区に同和地区のない学校では、生活の厳しい子どもたちへの働きかけがなかったり、子どもたちの心に響く部落問題学習がされなかったりした部分があったように感じています。
「同和教育は暗くてイヤだった」とはっきり言う学生は、こちらが働きかけるうえでのひっかかりがあるという意味ではまだよいと思います。多くの学生は「あまり印象がない」「あんなこと、わざわざ教えなくてもいいのに」と他人事のように言います。
これは部落問題と自分とをつなげられなかったということだと思います。部落出身かどうかにかかわらず、誰でも多かれ少なかれ心の隅に隠している葛藤や痛みや悩みがあるはずです。子どもたち同士がお互い自分のことをさらけ出し、そのやりとりを通して鍛えられ、成長する。そうした教育活動が土台にあれば、部落問題学習に対する印象も違っていたでしょう。
|
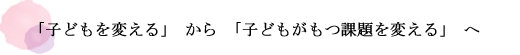 |
学生たちの多くが受けてきた同和教育は「部落の子」と「部落外の子」という枠組みを前に出してしまいがちだったようです。先に書いたような土台をきっちりつくって、自分たちのなかに悩みがあり、それが世の中とつながっているという実感をもてるようにしておかなければ、「私たちは違う」「かわいそうな人たちがいるみたい」というとらえ方になってしまいます。
本来、すべての人が差別性と被差別性の両方をもっているのです。ある差別と闘っている人が、ほかの場面では加害者や傍観者になるということも十分にありえます。つまり加害者や傍観者になるかどうかは、個人の人柄や生き方だけの問題ではないということです。
自分が、あるときは加害者になり、あるときには傍観者になったとすれば、なぜそんな違いが出てきたのかをふりかえることにより、いろいろ見えてくると思います。被害者(あるいは加害者)とどれほど近い関係だったのか、自分は強い立場にいたか、そのとき自分は何かをすべき役割をもっていたか。いろいろな要素があります。仲間を見つける、差別かどうかの見極め方を知るなど具体的な手段も必要です。
そのこととも関連して、ある教員の「子どもを変えるのではなく、子どもの直面している課題を変えるというふうに考えたほうがいいんじゃないか」という言葉に深くうなずいたことがあります。子どもを変えるという発想には、正しい自分が未熟な子どもを教え導くという視点があります。そうではなく、子ども自身が何を自分の課題だと思っているのかをとらえ、直面する課題を解決できるよう応援するのです。たとえば、荒れている子どもがいたとします。その子を変えようとすると、その子の生き方を変え、しっかりさせて荒れなくさせるというところに焦点を合わせる発想になりやすいでしょう。その子の直面している課題を変えようとすると、その子がなぜ荒れているのかを探り、荒れるようになった要因(課題)を子どもと一緒に解決していくことに焦点を合わせることになります。それは、ひょっとすると父親との関係を変えようとすることかもしれません。その生徒に対する同級生たちの見方を変えることかもしれません。実は、確かな視点をもって取り組んでいる教員は、「子どもを変える」という言葉を使ったとしても、ここでいう「子どもが直面している課題を変える」という取り組みを実質的にはしていたのです。
「子どもたちに生きる力を」と取り組まれてきた同和教育を土台に、さまざまな立場や個性をもつ人がともに取り組む「多様性教育」の枠組みをつくりあげていく時代だと感じています。
|