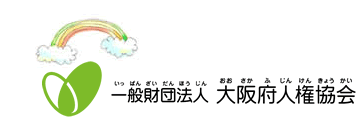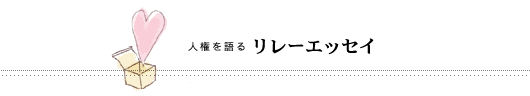|
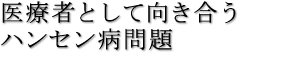 国立ハンセン病療養所邑久光明園 医師 青木 美憲(あおき・よしのり)さん |
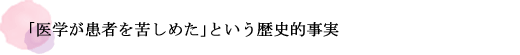 |
|
1998年、熊本地裁においてハンセン病訴訟が始まりました。ハンセン病療養所の入所者を中心に構成された原告団は、国に対して隔離政策をはじめとする人権侵害の責任を問いました。そして2001年の判決で国の過失がはっきりと認められたのです。
この裁判では医療従事者が訴えられることはありませんでした。しかしハンセン病の歴史を振り返ればわかるように、医者が隔離政策に深く関わっていたことは否定しようがありません。 わたしは北海道出身ですが、医学を志し、1987年に大学進学のため大阪へ来ました。そこで部落問題と出会い、人権について深く考えるようになりました。それまで人権といえばプライバシーのことかというぐらい、何も知りませんでした。 学生サークルの活動でハンセン病療養所の大島青松園を訪ねたのがきっかけでハンセン病問題と出会います。入所者の方の話から、患者さんの役に立つはずの医学が逆に苦しめてきた歴史があることを知りました。しかも当時はまだハンセン病問題は放置された状態でした。大きなショックを受けました。同時に医師としてこの問題から逃げてはならないと強く思いました。結果として就職先に国立ハンセン病療養所・邑久光明園を選び、現在に至っています。また、国賠訴訟では原告側の証人として、患者さんたちからの聞いた人権侵害の実態を話しました。 |
 |
|
ハンセン病と結核は病原体が原因であり、人から人に感染するという面でよく似た病気です。しかし結核の発病率が感染者の約10%であるのに対して、ハンセン病は1%以下です。今日の日本では0%といえます。しかも即、命に関わることはまれです。本来ならば隔離などの特別な対策は不要な病気です。ところが非常に嫌われる病となってしまった歴史があります。
その理由として、ハンセン病が皮膚と末梢神経を侵す病であることが挙げられます。しかも顔や手足という非常に目立つ部分が変形するので、美醜の感覚でとらえると「醜い」と映ってしまいます。これがハンセン病に対する差別の最も大きな原因ではないかと思われます。 ハンセン病に対する隔離政策が始まったのは1907年(明治40年)です。すでに経済状態の進展した欧米ではハンセン病患者が激減していました。先進国の仲間入りを目指す日本にとって、ハンセン病患者が集団生活や放浪をするのは非常に問題だったのです。そのため、放浪生活をする人たちの収容を目的に「らい予防に関する件」という法律がつくられました。 |
 |
|
1931年(昭和6年)、日本のハンセン病対策は大きく変わります。「らい予防法」と名前を変え、「ハンセン病を撲滅する」という目標が立てられました。そしてそのために全患者を強制的に隔離するという手段がとられたのです。
なぜそこまでしなければならないと考えたのか。まず、ハンセン病が非常に悪い疾患だという偏見がありました。人から人へ感染する病気であり、当時はまだ特効薬がありませんでした。遺伝するという誤解もありました。誤解や偏見が重なり、「らい菌をもっている人、すなわち患者を隔離して新たな感染を遮断することによってこの病気を撲滅する」という方法が考えられました。 また、当時の日本社会には全体主義思想が蔓延していました。社会を病気から守るためには患者の人権を犠牲にしても構わないという考え方です。さらに“汚い存在”であるハンセン病をなくすという民族浄化の思想や、患者さんの子孫を絶やして遺伝を防ぐという優性思想もあたり前のように存在していました。そのため患者を強制隔離し、治っても退所させない、子どもをつくることも許さないという大変な人権侵害が国策としてまかり通ったのです。 |
 |
|
この間、患者の側に立つべき医療関係者は何をしてきたのでしょうか。
1953年(昭和28年)、らい予防法を見直す機会がありました。当時すでに特効薬プロミンが使われるようになっていました。また民主憲法によって「基本的人権」という概念も広まりました。全国の療養所の入所者全員が加盟する患者団体がつくられ、国に対して隔離をやめるよう要望していました。しかしハンセン病医学の権威で「救らいの父」とまで言われた医師・光田健輔氏をはじめとする専門家たちは、国会で「隔離を強めるべきだ」と証言してしまったのです。結果として「らい予防法」は1996年まで続いてしまいました。このことはハンセン病の国賠訴訟でも大きな争点のひとつとなりました。そして判決では「1953年の時点で隔離を残す科学的根拠はまったくなかった」と明確に述べられています。 |
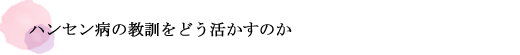 |
|
現在、日本においてハンセン病は終焉に向かっています。ハンセン病を発症する人は年間に一人か二人で、いずれゼロになるでしょう。全国で3500人ほどの入所者は高齢化が進み、年々その数は減少しています。しかし患者や療養所の入所者がゼロになれば、ハンセン病問題は解決したと言えるでしょうか。決してそうではないとわたしは考えます。
今も特定の感染症や疾患に対する偏見は根強くあります。感染症対策は確かに必要ですが、そこで患者の人権との両立をどのように図っていくのか。科学的な過ちを二度と起こさないために何が必要なのか。ハンセン病問題から学ぶことは多く、わたしたちはまだ十分に検証してはいません。今後の教訓としてどう生かしていくのかが重要な課題として残されているのです。 |