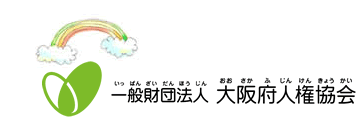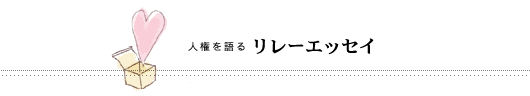|
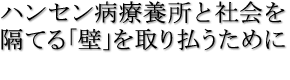 全国ハンセン病療養所入所者協議会 事務局長 神 美知宏(こう・みちひろ)さん |
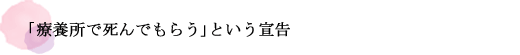 |
|
17歳でハンセン病を発病した時、わたしはハンセン病がどんな病気なのか、自分がどんな扱いを受けることになるのか、まったく知りませんでした。高校に退学届を出したものの、「病気が治れば学校に戻れる。一生懸命、治療に励もう」と思っていました。
いざ療養所へ行くと、いきなり絶望のどん底へ突き落とされました。まず名前を変えることを勧められました。ハンセン病患者が本名を使い続けることは、家族に迷惑がかかるということです。 さらに医師からは「治ったとしても療養所からは出さない」と言い渡され、解剖承諾書に署名、捺印をするよう求められました。「ここで死んでもらう」と宣告されたわけです。その場で「神崎正男」という名を自分につけた私は、「神美知宏という人間は抹殺されたのだ」と思い、生きる望みを失いました。 |
 |
|
療養所の中心部に、コンクリート造りの納骨堂があったのも衝撃的でした。療養所とは言いながら病気を治す場所ではなく、死んでいくのを待つ場所であることを象徴するものです。実際、全国ハンセン病療養所入所者協議会(全療協)の調査では、療養所で亡くなった約2万4千人のうち、65%が療養所の納骨堂で合祀されたままです。一部の療養所では98%もの人のお骨が納骨堂に納められています。ハンセン病患者は、死んでもなお家族の元や故郷には帰れないのです。
こうして絶望から始まった療養所生活でした。本来ならば未来への夢を描く青春時代に、生きていく希望も家族も何もかも失い、しばらくは死ぬことばかりを考えていました。ところが療養所のある職員がわたしをひとりの人間として認め、接してくれたのです。「自分は社会から抹殺された人間だ」と意気消沈していたわたしにとって、人生観がガラリと変わるほどの出来事でした。これをきっかけに生きる気力を取り戻し、療養所の自治会活動にも参加するようになりました。 |
 |
|
必死に治療しながら、自治会の活動を通じてハンセン病や強制隔離政策に関する歴史や事実を勉強しました。すると国がいかにひどい人権侵害を行っているかが見えてきたのです。「療養所に住んでいる人は人間扱いされていない。こんなことは絶対に許せない」と強く思い、運動にのめり込んでいきました。
入所から10年後、わたしは医師から完治を告げられました。社会復帰してもいいとも言われました。しかし学歴社会において、学歴も社会経験も特技もない自分がいきなり社会へ出ても何ができるでしょうか。家族に相談しても「おまえのいいようにしろ」と言うだけで、積極的に勧める空気はありませんでした。 とはいえまだ20代でしたから、まったく希望がなかったわけでもありません。けれども療養所に残る仲間を忘れることはできないと思いました。みんなのことが気になり、自分の生活に没頭できないであろうことは想像がつきました。 そこでわたしは決意したのです。「よし、俺は療養所で死んでもいい。ここでがんばろう」と。心を決めた後は、それまで以上に運動に熱が入りました。 |
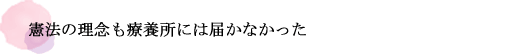 |
|
日本は戦後、基本的人権の尊重と民主主義を謳った日本国憲法をもちました。しかしハンセン病患者の人権を踏みにじる「らい予防法」は1996年まで生き残り続けました。憲法の理念など、療養所には無関係だったのです。法律がなくなり、国が過ちを認めた今も「差別」「排除」という被害を受け続けている人がいます。この非常に大きな問題を、どれほどの日本国民が知っているでしょうか。
少なくとも療養所の実態を身近で見てきた医療関係者や職員から「これはおかしい」という声がなぜ出なかったのか。らい予防法の改正に向けて日本弁護士会に支援を頼んだ時も、反応は鈍いものでした。「やっかいなものには手を出さない」という風潮が、専門家の間にすら浸透していたように思います。 しかし風向きは確実に変わっていきました。そして2001年、熊本地裁判決によって国の過ちが認定されたのです。国が控訴断念を決めるまでの2週間、わたしは初めて運動の先頭に立ち、首相官邸前で座り込みをしました。その時、多くの市民の人たちが我々と一緒に座り込みをしてくれました。長い間、運動をしてきましたが、あれほどの一般市民の人たちがわたしたちの運動を支持し、一緒に行動してくれたのは初めてでした。国の控訴断念は、市民の後押しがあったからこそだと思います。そしてわたしは「神美知宏」という名を取り戻しました。 |
 |
|
わたしたちが今後取り組まなくてはならないのは、ハンセン病療養所の「社会化」です。個人が社会復帰するというあり方も必要ですが、療養所そのものが社会と隔てられている垣根を取り払い、社会のなかへ入っていこうということです。具体的には家族と暮らせず、施設にも入れない高齢者を招き入れ、ともに暮らすというのもひとつの姿です。講演などで話すと非常に反響が大きいのですが、法律の壁があり、スムーズにはいきません。しかし療養所は医療や看護、介護の態勢が整い、リハビリ施設もあります。国民の税金で運営している施設を共有財産としてみんなが使えばいいのではないでしょうか。交流、共生することによって差別や偏見が少しずつでもなくなるのではという期待もあります。
こうした提案を積極的に社会へ投げかけ、国民的議論を盛り上げていきたい。高齢化したわたしたちにとっては時間との闘いでもあります。 |