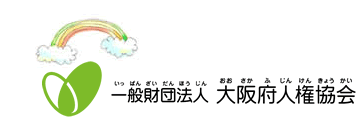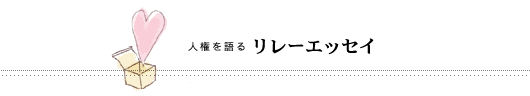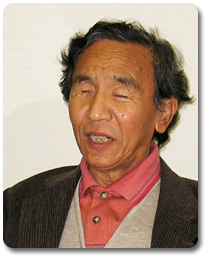 |
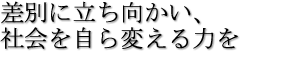 NPO法人 大阪障害者自立生活協会 理事長 楠 敏雄(くすのき としお)さん |
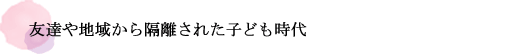 |
|
ぼくは2歳の時に医療ミスによって失明しました。まだ2歳ですから自分が「障害者」となったことを理解できるはずもありません。初めて自分の障害に気付いたのは、3歳の頃、友達に差別的な言葉を投げつけられた時です。自分はほかの子どもたちとは違うんだと知らされ、ショックと屈辱を感じました。そしてそれをずっとひきずっていたのです。
一方で、子どもたちとはつきあいのなかで友達になり、地域で一緒に遊ぶ友達もできました。つまり、差別はありながら、地域で生きるすばらしさも同時に感じることができたのです。それなのにぼくが盲学校へ行くことで友達と引き離され、寮生活のため地域からも隔離され、「健常者」の社会とは別の社会で生きることを強いられたのです。 盲学校から遠足に行くと、一般の学校の子どもたちと一緒になることがあります。すると「めくらが遠足に来ている」と笑われる。そんな時、盲学校の教師たちは「障害者はどんなことがあっても怒ってはダメだ。いつもニコニコしていなさい」とぼくらに言う。「何も悪いことをしていない自分たちが、なぜ我慢しなくちゃいけないのか。先生たちはいったい誰の味方なのか」と怒りを覚えました。社会にはびこる差別意識を思い知らされ続けた子ども時代でした。 |
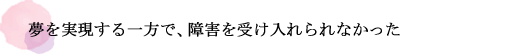 |
|
進路の問題でも壁が立ちはだかりました。中学校で英語を学び、やがて英語の教師になりたいという夢をもったのですが、高校進学の段階で「目の見えない者は、あんま・鍼・灸の仕事しかない。それを一生懸命やりなさい」と言われたのです。夢と希望を打ち砕かれ、絶望しました。それでも夢を捨て切れず、生まれ育った北海道を出て関西へ。そして一年の浪人の末に大学進学を果たしました。今では信じられない話ですが、「大学としては一切、協力しない」という条件つきの入学でした。かなり厳しい学生生活でしたが、友達の支えもあって卒業し、定時制高校の英語の教師として13年間、教壇に立ちました。
こうして数多くの差別に遭い、時に絶望しながらも差別に負けまいと生きていました。社会への憎しみや怒り、親や自分を失明に追い込んだ医者への恨みをずっと引きずりながら…。一方で、大学時代の私は白い杖を持つのが恥ずかしくて、一人で歩く時は自己防衛の手段として杖を持ちますが、友達がいる時には杖を小さく畳んでポケットにしまいこんでいました。自分を苦しめた社会が悪いと思いながら、自分は健常者として扱われたいという意識があったのです。 |
 |
|
そんなぼくの意識を大きく変える出会いがありました。ひとつは狭山事件です。石川一雄さんのことを知り、自分が感じてきた差別と通じるものを感じました。同時に、被差別部落に生まれ、差別されたからこそ、あらゆる差別に敏感で「差別を絶対に許さない」という情熱をもつ石川さんや部落解放運動の精神に心を揺さぶられました。差別に反発しながら、どこかで障害のある自分を恥じ、社会に遠慮する自分の姿が見えてきました。
脳性マヒの人たちのグループ、「青い芝の会」との出会いも大きなものでした。自らの障害をさらけ出して、障害者を醜いと思う社会の価値観を変えていく、そして自分たちも堂々と生きていく姿。また、障害児が生まれたことを恥ずかしく、あるいは不憫に思って殺してしまう親たちに対して「俺たちは殺されるのはイヤだ!」と訴えた。人殺しをしても同情する社会とは何だと告発したのです。 厳しい差別に正面から立ち向かう石川さんや「青い芝の会」のメンバーたちの主張、生き様に出会い、自分の生きてきた道を改めて振り返りました。障害があるのは恥ずかしいことではない。障害を受け入れ、差別に正面から立ち向かっていくような生き方をしなければダメだと気づきました。 |
 |
|
ぼくの障害者運動には、「反差別」「反隔離」「自己決定」という3つの柱があります。「反差別」とは、障害をもっているために人間として認められないことへの怒りです。施設のなかで管理されて生きるのではなく、リスクがあっても地域で健常者と一緒に生きていくなかで人間的な喜びを感じていくんだという思いが「反隔離」であり、そのためにも親や専門家ではなく、当事者が判断や選択をしていく「自己決定」が大切だということです。
30年前は「過激だ」と敬遠されたりもしましたが、今では社会のなかで当たり前のこととして受け止められています。それでは障害者が本当に暮らしやすい社会になったかというと、現実には差別や隔離によって苦しんでいる人たちがいるのです。一方で、若い世代を中心に「楽しく生きられればいい」と考える人が増え、運動の力が弱まっているように感じます。差別を笑いのネタにするような風潮にも忸怩(じくじ)たる思いがあります。 人間関係が途切れがちな今の社会では、人と人とのつながりを意識的につくる必要があります。障害者と健常者が普段のつきあいのなかで障害者問題や差別について語り合うことが、壁や差別をなくすことにつながってゆくと思うのです。 これからは視覚障害、精神障害といった障害の種別を超え、また在日外国人、女性、部落といった被差別の立場にいる人たちとも連帯し、お互いを学びあうことが大切だと考えています。それも団結するだけでなく、今の社会のあり方や人間の生き方を問い直し、政治や法律の現場で発言していく。誰かに「何とかしてもらおう」ではなく、自分たちに力をつけて社会を変えていく。そんな運動をこれからも目指したいと考えています。 |