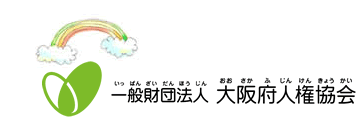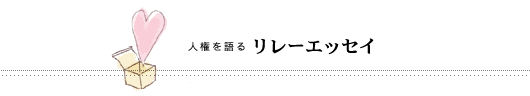|
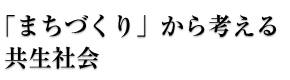 大阪市立大学大学院 創造都市研究科 教授 野口 道彦 さん |
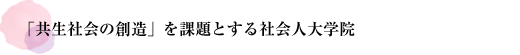 |
||
私の所属しているのは大阪市立大学の創造都市研究科です。昨年2003年の4月に発足した社会人向けの大学院です。8つの分野がありますが、そのうちの都市共生社会研究分野を他の6人の教員とともに担当しています。この分野は、「共生社会」と「NPO」をキー・コンセプトにあげた日本で初めての大学院です。未知の分野でありながら、人権問題やNPOで相当のキャリアを積んだ人たちがたくさん応募されました。「共生社会の創造」というメッセージが、チャレンジ精神をかきたてたのだろうと思います。これからも共生社会づくりをめざす意欲的な人たちに来ていただいて、創造都市のための知のセンターにしていきたいと考えています。 |
||
 |
||
近頃、「共生」という言葉がさまざまところで語られるようになりました。本のタイトルに、この言葉がどのように使われだしたのか調べてみました。1970年代はほとんどありませんが、85年ごろから増えはじめ、90年代にはいると爆発的に流行します。それとともに意味も拡散し、「共生のマーケティング」とか「病との共生」といった使われかたまでされるようになります。 「共生」とは非常に耳ざわりのいい、誰にでもスッと受け入れられる言葉なのでしょうね。行政のマスタープランづくりでも、「違いを認め合い、ともに生きる」という意味合いで、「共生社会」という言葉がよく登場するようになります。それはそれでいいのですが、なにか肝心なものが忘れられているのではないかと気になります。 「共生社会」には、このような「違いを認め合い、ともに生きる」という甘口の概念もありますが、もう一方で辛口の概念も忘れてはいけないと思います。現実の社会にある、不平等や差別から目をそらさず、それをどう変えていくのかという視点です。だから、「同化を強要されないこと」「力関係における対等性」「支援するものと支援されるものが固定的でない双方向型の関係」「機会の平等性、社会的資源への平等なアクセス」ができているのかをたえず問うていくことが大切で、「わたしたちは、共生しているのだ」と安住してしまうと、とたんにおかしくなると思います。 |
||
 |
||
それは、ひとことで言えば「関係性」です。部落と部落外、障害者と健常者、女性と男性……と並べてみると、マイノリティ(少数派、力をもたない側)とマジョリティ(多数派、力をもつ側)というのは、力関係に強弱の差があるというだけではなく、そもそも両者の関係が、非対称的な関係であるということがわかります。例えていえば、ある日突然差別されることによって、本人がどう思おうと関係なく「部落民とみなされてしまう」のです。否も応もなく、そのような枠組みのなかにはめられてしまうという理不尽さがあるのです。そのような土俵(マイノリティにとっては否応なく設定された場)で戦わざるを得ないのです。 こうした不条理は、目にみえにくいものです。その上に、機会の不平等や資源の不平等な配分が重なっています。こちらの方は、目にみえやすいものです。もちろん、この二つの構造を変えていかねばならないわけです。マジョリティにとっては安住している場が問われるし、自己批判を迫られる厳しいものです。共生社会をめざすということは、それほど口当たりのいいものではありません。それを受け入れる覚悟があるかどうかが問われることになります。 |
||
 |
||
これまではシングル・イシューの時代であったと思います。つまり部落問題なら部落差別をなくすことだけを追及してきました。障害者問題しかり、在日外国人問題しかり。しかし近年、マイノリティ社会のなかにも、さらに差別があるという問題提起がされるようになりました。たとえば部落問題のなかにも女性差別、障害者差別が存在する。女性の間にも部落差別があり、障害者差別があるという問題です。このような「複合差別」にどのように取り組んでいくのか、簡単ではありません。他方では、マジョリティの側から、「君らの中にも、差別があるじゃないか。偉そうに、差別、差別というな」と、マイノリティの足下をすくうような声も出てきます。互いに、「どっちもどっちだ」と言い合っていては、前には進みません。「敵に弱みを見せるな」といって、内部の矛盾を隠蔽するのは、内部の弱者を抑圧することになります。関係はねじれたり、こんぐらがったりして、一筋縄でいきません。難しいといって逃げていることはできません。もつれ合った糸をほどいていくことが、共生社会をめざすわれわれに問われているのです。 それでは具体的にどんな取り組みができるのか。私は部落における「まちづくり」がひとつのモデル・ケースになるのではないかと思っています。 |
||
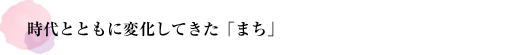 |
||
まちづくりは住宅や道路、公園といったハードだけでなく、人と人との関係のありかたが重要です。学校では、教師に反抗してばかりいる子も、家では親孝行の子もいます。学校で荒れている子も、地域の子どもの面倒を見たりして、「いいお兄ちゃん」である場合もあります。子どもは学校だけで育つわけではありません。地域がもつ教育力があります。 一方で、人々が流動化し、互いに無関心になっている都市では、地域のもつ教育力が格段に衰えてきています。子どもに注意すると、仕返しをされるかもわからないと恐れる大人が増えてきており、他人には無関心を装っています。 部落では、近所の子どもでも「ご飯食べたか。うちで食べていきや」と声を掛け合った記憶が残っています。だんだんとなくなってきたと言われますが、まだ部落には教育力があります。子どもに声を掛け合ったり、助け合ったりする力です。これをまちづくりにどのように再生させるのか問われています。 |
||
 |
||
特別措置法時代が終わり、同和地区内の住宅の入居についても、地域コミュニティの形成を図る新たな入居システムの構築が図られ、今まで以上に地区外から多様な人が転入するようになります。現実には、生活が安定した層が出て行き、部落出身ではないが経済的あるいは身体的なハンディを負った人たちが「住みやすいまち」として移り住むようになる傾向は、ますます強まるでしょう。 私は、ふたつの道があると思います。安定した層が出て行った後に入ってくる、さまざまな課題を抱えた人たちを積極的に受け入れ、そのような人たちも主人公として参加していくまちづくりを目指す方向が一つ。もう一つは、安定した層が出てゆかないような魅力あるまちづくり、経済的にも多様な階層が住み続けられるようなバラエティーに富んだ住宅を提供し、多様な価値観やライフスタイルをもった人にも魅力あるまちにしていく方向。そのどちらを自主的に、主体的に選択するのかということが、今まさに問われているのだと思います。 そうではなく、このまま流れに流されていけば、最悪のパターンです。それぞれの事情を抱えて入ってきた人たちは必ずしも地域に愛着があるわけでもないし、「仮住まい」という意識も強い。「このまちをよくしていこう」という気構えがない人たちが増えてゆき、貧しさの再生産。しかも、貧しいからこそ助け合ってきた良さはなくなり、近所の子どもがタバコやシンナーを吸っていても、こわくて注意できないという無干渉・無関心で、冷たいまちになっていくという事態です。 そうならないために、どうすればよいのか皆の知恵を出し合う必要があります。これまで蓄積してきた部落解放運動の力やノウハウを活かすことができれば、「共生社会」づくりへの大きな第一歩が踏み出せます。逆に、活かし切れなければ部落解放運動そのものが立ち行かなくなってしまう恐れがあります。これからの5年10年が、部落解放運動の正念場になるだろうと思います。 これは同和地区の将来だけにかかわる話ではなく、共生社会をどのようにつくっていくのか、そのモデル・ケースになります。大きな期待が寄せられています。 |
||